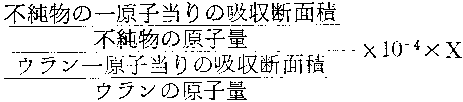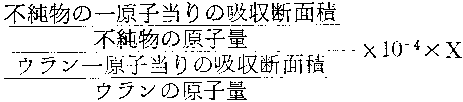
○そ の 他
アルゼンティン、オーストラリア、ベルギー、チリ、フランス共和国、日本国、ニュー・ジーランド、ノールウェー、南アフリカ連邦、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の政府は、
南極地域がもつぱら平和的目的のため恒久的に利用され、かつ、国際的不和の舞台又は対象とならないことが、全人類の利益であることを認め、
南極地域における科学的調査についての国際協力が、科学的知識に対してもたらした実質的な貢献を確認し、
国際地球観測年の間に実現された南極地域における科学的調査の自由を基礎とする協力を継続し、かつ、発展させるための確固たる基礎を確立することが、科学上の利益及び全人類の進歩に沿うものであることを確信し、
また、南極地域を平和目的のみに利用すること及び南極地域における国際間の調和を継続することを確保する条約が、国際連合憲章に掲げられた目的及び原則を助長するものであることを確信して、
次のとおり協定した。
第一条
1 南極地域は、平和的目的のみに利用する。軍事基地及び防備施設の設置、軍事演習の実施並びにあらゆる型の兵器の実験のような軍事的性質の措置は、特に、禁止する。
2 この条約は、科学的研究のため又はその他の平和的目的のために、軍の要員又は備品を使用することを妨げるものではない。
第二条
国際地球観測年の間に実現された南極地域における科学的調査の自由及びそのための協力は、この条約の規定に従うことを条件として、継続するものとする。
第三条
1 締約国は、第二条に定めるところにより南極地域における科学的調査についての国際協力を促進するため、実行可能な最大限度において、次のことに同意する。
(a) 南極地域における科学的計画の最も経済的なかつ能率的な実施を可能にするため、その計画に関する情報を交換すること。
(b) 南極地域において探検隊及び基地の間で科学要員を交換すること。
(c) 南極地域から得られた科学的観測及びその結果を交換し、及び自由に利用することができるようにすること。
2 この条の規定を実施するに当り、南極地域に科学的又は技術的な関心を有する国際連合の専門機関及びその他の国際機関との協力的活動の関係を設定することを、あらゆる方法で奨励する。
第四条
1 この条約のいかなる規定も、次のことを意味するものと解してはならない。
(a) いずれかの締約国が、かつて主張したことがある南極地域における領土主権又は領土についての請求権を放棄すること。
(b) いずれかの締約国が、南極地域におけるその活動若しくはその国民の活動の結果又はその他の理由により有する南極地域における領土についての請求権の基礎の全部又は一部を放棄すること。
(c) 他の国の南極地域における領土主権、領土についての請求権又はその請求権の基礎を承認し、又は否認することについてのいずれかの締約国の地位を害すること。
2 この条約の有効期間中に行なわれた行為又は活動は、南極地域における領土についての請求権を主張し、支持し、若しくは否認するための基礎をなし、又は南極地域における主権を設定するものではない。南極地域における領土についての新たな請求権又は既存の請求権の拡大は、この条約の有効期間中は、主張してはならない。
第五条
1 南極地域におけるすべての核の爆発及び放射性廃棄物の同地域における処分は、禁止する。
2 核の爆発及び放射性廃棄物の処分を含む核エネルギーの利用に関する国際協定が、第九条に定める会合に代表者を参加させる権利を有するすべての締約国を当事国として締結される場合には、その協定に基づいて定められる規則は、南極地域に適用する。
第六条
この条約の規定は、南緯六十度以南の地域(すべての氷だなを含む。)に適用する。ただし、この条約のいかなる規定も、同地域内の公海に関する国際法に基づくいずれの国の権利又は権利の行使をも害するものではなく、また、これらにいかなる影響をも及ぼすものではない。
第七条
1 この条約の目的を促進し、かつ、その規定の遵守を確保するため、第九条にいう会合に代表者を参加させる権利を有する各締約国は、この条に定める査察を行なう監視員を指名する権利を有する。監視員は、その者を指名する締約国の国民でなければならない。監視員の氏名は、監視員を指名する権利を有する他のすべての締約国に通報し、また、監視員の任務の終了についても、同様の通告を行なう。
2 1の規定に従つて指名された各監視員は、南極地域のいずれかの又はすべての地域にいつでも出入する完全な自由を有する。
3 南極地域のすべての地域(これらの地域におけるすべての基地、施設及び備品並びに南極地域における貨物又は人員の積卸し又は積込みの地点にあるすべての船舶及び航空機を含む。)は、いつでも、1の規定に従つて指名される監視員による査察のため開放される。
4 監視員を指名する権利を有するいずれの締約国も、南極地域のいずれかの又はすべての地域の空中監視をいつでも行なうことができる。
5 各締約国は、この条約がその国について効力を生じた時に、他の締約国に対し、次のことについて通報し、その後は、事前に通告を行なう。
(a) 自国の船舶又は国民が参加する南極地域向けの又は同地域にあるすべての探検隊及び自国の領域内で組織され、又は同領域から出発するすべての探検隊
(b) 自国の国民が占拠する南極地域におけるすべての基地
(c) 第一条2に定める条件に従つて南極地域に送り込むための軍の要員又は備品
第八条
1 この条約に基づく自己の任務の遂行を容易にするため、第七条1の規定に基づいて指名された監視員及び第三条(1)(b)の規定に基づいて交換された科学要員並びにこれらの者に随伴する職員は、南極地域におけるその他のすべての者に対する裁判権についての締約国のそれぞれの地位を害することなく、南極地域にある間に自己の任務を遂行する目的をもつて行なつたすべての作為又は不作為については、自己が国民として所属する締約国の裁判権にのみ服する。
2 1の規定を害することなく、南極地域における裁判権の行使についての紛争に関係する締約国は、第九条1(e)の規定に従う措置が採択されるまでの間、相互に受諾することができる解決に到達するため、すみやかに協議する。
第九条
1 この条約の前文に列記する締約国の代表者は、情報を交換し、南極地域に関する共通の利害関係のある事項について協議し、並びに次のことに関する措置を含むこの条約の原則及び目的を助長する措置を立案し、審議し、及びそれぞれの政府に勧告するため、この条約の効力発生の日の後二箇月以内にキャンベラで、その後は、適当な間隔を置き、かつ、適当な場所で、会合する。
(a) 南極地域を平和的目的のみに利用すること。
(b) 南極地域における科学的研究を容易にすること。
(c) 南極地域における国際間の科学的協力を容易にすること。
(d) 第七条に定める査察を行なう権利の行使を容易にすること。
(e) 南極地域における裁判権の行使に関すること。
(f) 南極地域における生物資源を保護し、及び保存すること。
2 第十三条の規定に基づく加入によりこの条約の当事国となつた各締約国は、科学的基地の設置又は科学的探検隊の派遣のような南極地域における実質的な科学的研究活動の実施により、南極地域に対する自国の関心を示している間は、1にいう会合に参加する代表者を任命する権利を有する。
3 第七条にいう監視員からの報告は、1にいう会合に参加する締約国の代表者に送付する。
4 1にいう措置は、その措置を審議するために開催された会合に代表者を参加させる権利を有したすべての締約国により承認された時に効力を生ずる。
5 この条約において設定されたいずれかの又はすべての権利は、この条に定めるところによりその権利の行使を容易にする措置が提案され、審議され、又は承認されたかどうかを問わず、この条約の効力発生の日から行使することができる。
第十条
各締約国は、いかなる者も南極地域においてこの条約の原則又は目的に反する活動を行なわないようにするため、国際連合憲章に従つた適当な努力をすることを約束する。
第十一条
1 この条約の解釈又は適用に関して二国以上の締約国間に紛争が生じたときは、それらの締約国は、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決又はそれらの締約国が選択するその他の平和的手段により紛争を解決するため、それらの締約国間で協議する。
2 前記の方法により解決されないこの種の紛争は、それぞれの場合にすべての紛争当事国の同意を得て、解決のため国際司法裁判所に付託する。もつとも、紛争当事国は、国際司法裁判所に付託することについて合意に達することができなかつたときにも、1に掲げる各種の平和的手段のいずれかにより紛争を解決するため、引き続き努力する責任を免れない。
第十二条
1(a) この条約は、第九条に定める会合に代表者を参加させる権利を有する締約国の一致した合意により、いつでも修正し、又は改正することができる。その修正又は改正は、これを批准した旨の通告を寄託政府が前記のすべての締約国から受領した時に、効力を生ずる。
(b) その後、この条約の修正又は改正は、他の締約国については、これを批准した旨の通告を寄託政府が受領した時に、効力を生ずる。他の締約国のうち、(a)の規定に従つて修正又は改正が効力を生じた日から二年の期間内に批准の通告が受領されなかつたものは、その期間の満了の日に、この条約から脱退したものとみなされる。
2(a) この条約の効力発生の日から三十年を経過した後、第九条に定める会合に代表者を参加させる権利を有するいずれかの締約国が寄託政府あての通報により要請するときは、この条約の運用について検討するため、できる限りすみやかにすべての締約国の会議を開催する。
(b) 前記の会議において、その会議に出席する締約国の過半数(ただし第九条に定める会合に代表者を参加させる権利を有する締約国の過半数を含むものとする。)により承認されたこの条約の修正又は改正は、その会議の終了後直ちに寄託政府によりすべての締約国に通報され、かつ、1の規定に従つて効力を生ずる。
(c) 前記の修正又は改正がすべての締約国に通報された日の後二年の期間内に1(a)の規定に従つて効力を生じなかつたときは、いずれの締約国も、その期間の満了の後はいつでも、この条約から脱退する旨を寄託政府に通告することができる。その脱退は、寄託政府が通告を受領した後二年で効力を生ずる。
第十三条
1 この条約は、署名国によつて批准されるものとする。この条約は、国際連合加盟国又は第九条に定める会合に代表者を参加させる権利を有するすべての締約国の同意を得てこの条約に加入するよう招請されるその他の国による加入のため開放される。
2 この条約の批准又はこれへの加入は、それぞれの国がその憲法上の手続に従つて行なう。
3 批准書及び加入書は、寄託政府として指定されたアメリカ合衆国政府に寄託する。
4 寄託政府は、すべての署名国及び加入国に対し、批准書又は加入書の寄託の日並びにこの条約及びその修正又は改正の効力発生の日を通報する。
5 この条約は、すべての署名国が批准書を寄託した時に、それらの国及び加入書を寄託している国について、効力を生ずる。その後、この条約は、いずれの加入国についても、その加入書の寄託の時に効力を生ずる。
6 この条約は、寄託政府が国際連合憲章第百二条の規定に従つて登録する。
第十四条
この条約は、ひとしく正文である英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により作成し、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する、同政府は、その認証謄本を署名国政府及び加入国政府に送付する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、正当に委任を受け、この条約に署名した。
千九百五十九年十二月一日にワシントンで作成した。
アルゼンティンのために
アドルフォ・シリンゴ
F・ベリョ
オーストラリアのために
ハワード・ビール
ベルギーのために
オペール・ドゥ・ティユージー
チリのために
マルシャル・モラ・M
E・ガハルド・V
フリオ・エスクデーロ
フランス共和国のために
ピエール・ジャルパンティエ
日本国のために
朝海浩一郎
下田 武三
ニュー・ジーランドのために
G・D・L・ホワイト
ノールウェーのために
パウル・コート
南アフリカ連邦のために
ヴェンツェル・C・ドゥ・ブレッシス
ソヴィエト社会主義共和国連邦のために
V・クズネツォフ
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国のために
ハロルド・キャッシャ
アメリカ合衆国のために
ハーマン・フレーガー
ポール・C・ダニエルズ
研究用原子炉計画(JRR-3)のためのウランの供給についての日本国政府に対する国際原子力機関による援助に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定
前 文
日本国政府は、国際原子力機関憲章第十一条の規定に基き、平和的目的のための原子力の研究計画に必要な原料物質を同政府に対して売却することについての国際原子力機関の援助を要請したので、国際原子力機関の理事会は、機関憲章に従つて前記の計画を検討し、かつ、承認したので、
日本国政府(以下「政府」という。)及び国際原子力機関(以下機関という。)とは、機関がその憲章に従つて当該計画に対し物質及び役務を供給することに関し、同憲章に掲げるすべての条件及び規定に従うことを条件として、次のとおり協定した。
第一条 物質の割当
機関は、この協定の附属書Aに掲げる計画に対し、附属書Bにその仕様が記載されている天然ウラン金属(以下「原料物質」という。)を割り当てる。機関は、政府の要請を受けたときは、計画に対し、別段の合意がない限り第三条及び第五条の条件に従つて役務及び追加の物質を割り当てることができる。
第二条 売却の条件
次の条件に従つて、機関は、三千キログラムから三千二百キログラムまでの量の原料物質を売却し、政府は、同原料物質を購入するものとする。
(a) 政府は、この協定の効力発生の日から三十日以内に、原料物質の引渡を受けることを希望するカナダ内の場所を指定しなければならない。機関は、政府との協議の後、政府に対し、前記の場所における原料物質の引渡の時期及び引き渡すべき原料物質の正確な重量について、四週間以上の予告をもつて通告しなければならない。機関は、千九百五十九年十一月一日以前に原料物質の引渡を行うことを確保するよう最善の努力を払うものとする。
(b) 機関は、(a)の規定に従つて機関が定める時期において、政府との協議の後機関が指定する場所で政府の代表者に適当な文書を交付することにより、原料物質についての権原を移転するものとする。同時に、政府は、その要請によつて供給される三千二百キログラムを限度とする原料物質及びその見本について一キログラムにつき三五・五〇合衆国ドルの割合の金額を機関に支払うものとし、この支払金は、この協定に基いて機関に支払われるべき全料金とする。権原移転の文書の交付及び支払が行なわれた日から四日以内に、政府は、(a)の規定に従つて政府が指定した場所において原料物質を取得するものとする。
(c) この協定の効力発生後直ちに、政府は、検査のために必要とする原料物質の代表的な見本の適当な量について機関に通告するものとし、また、政府がその見本の採取及び危険係数の計測を監査するために代表者を派遣することを希望するかどうかを機関に通告するものとする。前記の見本は、機関が見本を採取すると同じ時に採取され、かつ、機関により政府に提供されるものとする。機関は、政府に対し、機関がみずから行い、又は機関の費用で行われる原料物質の見本の採取及び見本の検査又は計測を監査するために代表者を派潰することを許すものとし、また、その検査及び計測の結果を政府に提供するものとする。
(d) 機関が最善の努力を払つたにもかかわらず、原料物質の売却者としての責任を果さなかつたときは、機関が政府に支払う損害賠償金は、(b)の規定に基き機関に支払われた額から機関が負担した実際の取扱費を減じたものを限度額とする。この損害賠償の請求は、原料物質の権原が政府に移転した日から一年以内に機関に通告しなければならない。
(e) 政府が行つた原料物質の化学分析又は全炉物理的不純物係数の計測が最大許容限度をこえる不純物又は全炉物理的不純物係数を示すときは、機関は、その申し立てられた一又は二以上の不純物について、審判者としての連合王国国立化学研究所(イングランド州ミドルセックス県テディントン)又は審判者として合意された他の研究所による分析を要求することができ、また同様に、全炉物理的不純物係数について、審判者としての連合王国原子力研究所(イングランド州バークシャー県ハーウェル)又はその計測について審判者として合意された他の研究所による計測を要求することができる。審判者によるその分析及び(又は)計測の結果は、最終的かつ拘束的なものとする。審判者によつて決定された不純物含有量又は危険係数が最大許容限度をこえる場合には、その分析及び(又は)計測の費用は、機関が負担するものとし、他の場合には、その分析及び(又は)計測の費用は、政府が負担するものとする。
第三条 機関の保障措置
1 政府は、この協定に基いて又はこの協定の範囲内において機関により提供される原料物質及びその使用により生産される特殊核分裂性物質が、いかなる軍事的目的をも助長するような方法で使用されないことに同意する。政府は、さらに、前記の原料物質が、あらかじめ機関の書面による同意を得ることなしに、この協定の附属書Aに掲げる計画以外の目的に使用されないこと、及び前記の原料物質及びその使用により生産される特殊核分裂性物質が、あらかじめ機関の書面による同意を得る場合を除き、日本国外又は政府の管理外に移転されないことに同意する。
2 機関憲章第十二条Aに定める保障措置(保健上及び安全上の措置を含む。)は、機関及び政府の間で機関憲章に従つて別段の合意を行う時まで、計画に関連するものであることが合意され、かつ、明記される。機関の理事会が採択することがある関係一般規則及び前記の憲章の規定に従うことを条件として、機関の保障措置の適用に関する細目は、機関の事務局長が政府と協議した後、機関の理事会が随時決定するものとする。政府は、機関が設定することのあるいずれの要求措置にも従い、かつ、その実施について機関と協力することに同意する。
3 政府は、計画の承認の際に機関による検討のために政府が提出した保健上及び安全上の基準及び措置を遵守し、及び適用し、並びに、この協定の規制を受ける操作に適用されうる限り、また、機関がそれらの基準及び措置に追加又は変更を行うことについてあらかじめ通報を受け、かつ、これに反対しない場合を除き、追加又は変更を行わないことに同意する。機関又は政府のいずれか一方が新たな事情にかんがみ前記の基準及び措置について追加又は変更を行うべきであると認めるときは、機関と政府との間に協議を行うものとする。
4 この条の規定に基く機関の保障措置の適用に関して問題又は紛争が生じた場合には、機関の理事会の決定は、直ちに効力を生ずるものとし(ただし、その旨の定があるときに限る)その問題又は紛争に関して執られるか又は執られた協議、交渉、又は仲裁のいずれかの手続の結果が判明するまでの間、政府により遵守されなけれはならない。
第四条 情 報
政府は、機関憲章第八条に定める情報の交換に関する機関の任務遂行を容易にすることを約束する。
機関は、この計画に対する援助の程度にかんがみ、この計画から生ずる発明若しくは発見についてのいかなる権利若しくは利益又はそれに関連するいかなる特許権も請求することはない。もつとも、機関は、合意される条件に従つて前記の特許権に基く実施権を許与されることができる。
第五条 紛争の解決
この協定の解釈又は適用に関する問題又は紛争で交渉により解決されないものは、解決の方法について第二条(e)に定めるものを除き、機関又は政府のいずれかの要請により、三人の構成員、すなわち政府が指名する一人、機関の事務局長が指名する一人及びこれらの二人が共同して指名する主宰者たる第三の構成員からなる仲裁裁判所に付託するものとする。要請を行つた後三箇月以内に最初の二人の構成員が第三の構成員の指名について意見が一致しなかつたときは、第三の構成員は、国際司法裁判所長が指名する。仲裁裁判所の過半数による決定(手続、管轄権及び当事者間の裁判費用の分担に関するすべての裁定を含む。)は、両当事者を拘束する。前記の決定は、両当事者がそれぞれ憲法上及び憲章上の手続に従つて実施するものとする。仲裁裁判所の構成員の報酬は、国際司法裁判所規程第三十二条4に基く国際司法裁判所の特別裁判官と同一の基礎において定められるものとする。
第六条 効 力 発 生
この協定は、正当に委任を受けた政府の代表及び機関の事務局長により署名された時に効力を生ずるものとする。
千九百五十九年三月二十四日にウィーンで、英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
古内 廣雄
国際原子力機関のために
スターリング・コール
附属書A 計画の定義
この協定が関係する計画とは、日本原子力研究所が日本国におけるその東海研究所に建設し、かつ、操作するJRR-3と呼称される熱出力十メガワットの天熱ウラン燃料=重水減速=重水冷却型研究用原子炉とその関連施設をいう。
附属書B 原料物質の仕様
1 物 質
金属ウラン(同位元素の組成が天然のままのもの)
2 形及び大きさ
金属ウランは、鍜造したビレットの形状で提供する。
長さ 五〇センチメートル
断面 一五センチメートル×一五センチメートル(ただし、角取りを施す。)
3 密 度
平 均 一立方センチメートルにつき一八・九五グラム
最小限度 一立方センチメートルにつき一八・九グラム
4 結晶粒度
最大限度 直径二〇〇ミクロン
最小限度 直径五〇ミクロン
5 結晶軸の方向性
不 整
6 表面処理条件
提供時の鍜造ビレットは、表面のスケール及び酸化物を除去するため五〇パーセント硝酸液で酸洗される。シーム、スレバ及びラップの表面突出物は、表面処理によつて除去される。可視の深さが〇・五センチメートルをこえる縦方向の傷、横方向のクラック、側面のひび又は両端の割れ目のないことを保証するため、出荷に先だち検査を行う。
提供される金属ウランは、圧延その他の加工に供することができる。
各ビレットにつき 〇・二五パーセント以下
全ビレットの平均 〇・二〇パーセント以下
8 化学的分析
不純物(単位・重量 百万分率)
| 保証最大限 | 保証最小限 | 全インゴット又は全ビレットの平均 | |
| (各インゴット又は各ビレットにつき) | (各インゴット又は各ビレットにつき) | ||
| アルミニウム | 二〇 | 一〇 | 一五 |
| 硼 素 | 〇・二 | 〇・一 | 〇・一五 |
| カドミウム | 〇・一 | 〇・一をこえないものとする。 | 〇・一をこえないものとする。 |
| 炭 素 | 四〇〇 | 一〇〇 | 特別の要求による。 |
| クローム | 二〇 | 一〇 | 一二 |
| コバルト | 一・〇 | 一・〇をこえないものとする。 | 一・〇をこえないものとする。 |
| 鉄 | 一〇〇 | 六五 | 八〇 |
| ニッケル | 五〇 | 二五 | 三五 |
| 窒 素 | 四〇 | 二〇 | 三〇 |
| 硅素・硅酸 合計 | 五〇 | 三〇 | 四〇 |
| 水 素 | 一〇 | 五・〇 | 八・〇 |
| マグネシウム | 三〇 | 一五 | 二〇 |
| マンガン | 五・〇 | 二・〇 | 三・〇 |
一九五九年十一月二十日 国連第十四総会において採択
前 文
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権と人間の尊厳及び価値とに関する信念をあらためて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
国際連合は、世界人権宣言において、すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、同宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有する権利を有すると宣言したので、
児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法律上の保護を含めて、特別にこれを守り、かつ、世話することが必要であるので、
このような特別の保護が必要であることは、一九二四年のジュネーブ児童権利宣言に述べられており、また、世界人権宣言並びに児童の福祉に関係のある専門機関及び国際機関の規約により認められているので、
人類は、児童に対し、最善のものを与える義務を負うものであるので、
よつて、ここに、国際連合総会は、
児童が、幸福な生活を送り、かつ、自己と社会の福利のためにこの宣言に掲げる権利と自由を享有することができるようにするため、この児童権利宣言を公布し、また、両親、個人としての男女、民間団体、地方行政機関及び政府に対し、これらの権利を認識し、次の原則に従つて漸進的に執られる立法その他の措置によつてこれらの権利を守るように努力することを要請する。
第一条
児童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いかなる例外もなく、自己又はその家族のいずれについても、その人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利を考えられなければならない。
第二条
児童は、特別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することができるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなければならない。この目的のために法律を制定するに当つては、児童の最善の利益について、最高の考慮が払われなければならない。
第三条
児童は、その出生の時から姓名及び国籍をもつ権利を有する。
第四条
児童は、社会保障の恩恵を受ける権利を有する。児童は、健康に発育し、かつ、成長する権利を有する。この目的のため、児童とその母は、出産前後の適当な世話を含む特別の世話及び保護を与えられなければならない。児童は、適当な栄養、住居、レクリエーション及び医療を与えられる権利を有する。
第五条
身体的、精神的又は社会的に障害のある児童は、その特殊な事情により必要とされる特別の治療、教育及び保護を与えられなければならない。
第六条
児童は、その人格の完全な、かつ、調和した発展のため、愛情と理解とを必要とする。児童は、できるかぎり、その両親の愛護と責任の下で、また、いかなる場合においても、愛情と道徳的及び物質的保障とのある環境の下で育てられなければならない。幼児は、例外的な場合を除き、その母から引き離されてはならない。社会及び公の機関は、家庭のない児童及び適当な生活維持の方法のない児童に対して特別の養護を与える義務を有する。子供の多い家庭に属する児童については、その援助のため、国その他の機関による費用の負担が望ましい。
第七条
児童は、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等の段階においては、無償かつ、義務的でなければならない。児童は、その一般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教育を与えられなければならない。
児童の教育及び指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、まず第一に児童の両親にある。
児童は、遊戯及びレクリエーションのための充分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及びレクリエーションは、教育と同じような目的に向けられなければならない。社会及び公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない。
第八条
児童は、あらゆる状況にあつて、最初に保護及び救済を受けるべき者の中に含められなければならない。
第九条
児童は、あらゆる放任、虐待及び搾取から保護されなければならない。児童は、いかなる形態においても売買の対象にされてはならない。
児童は、適当な最低年令に達する前に雇用されてはならない。児童は、いかなる場合にも、その健康及び教育に有害であり、又はその身体的、精神的若しくは道徳的発達を妨げる職業若しくは雇用に、従事させられ又は従事することを許されてはならない。
第十条
児童は、人種的、宗教的その他の形態による差別を助長するおそれのある慣行から保護されなければならない。児童は、理解、寛容、諸国民間の友愛、平和及び四海同胞の精神の下に、また、その力と才能が、人類のために捧げられるべきであるという充分な意識のなかで、育てられなければならない。
第三十三回臨時国会における岸内閣総理大臣の演説(外交に関する部分)
(前 略)
ヴィエトナムに対する賠償問題に関しましては、本年五月サイゴンにおいてわが国との間に協定の調印を終えたのでありますが、これをもつて、ビルマ、フィリピン及びインドネシアに次いで、わが国が条約上賠償義務を負つているアジア諸国との間の賠償協定の締結は、完了するわけであります。私は、また、これを契機として、わが国とヴィエトナムとの友好関係が増進され、ひいては貿易、海運等各分野における両国間の関係が、一層緊密なものとなることを確信いたします。
(中 略)
私は、さる七月、八月の両月にわたり、約一カ月欧州及び中南米各国を訪問して、それぞれの政府首脳者と意見の交換を行ない、親しく現地の情勢をみてまいりました。この間、各国首脳者との会談を通じて痛感いたしましたことは、国際場裡におけるわが国の地位と役割がとみに重きを加えつつあるということであります。また、東西両陣営の接触点たるヨーロッパにおきましては、集団安全保障体制の強化、あるいは、いわゆる欧州統合化の推進等自由主義陣営の強化について非常な努力がみられ、主要各国首脳が一致して考えているところも、自由主義諸国の結束の強化と、それを背景にした話し合いによる平和の実現ということでありました。この意味におきましてわが国といたしましては、欧州におけるこれら諸国との友好関係を、今後とも促進する必要を痛感した次第であります。
政府は、つとに日米両国の関係の改善を企図して、わが国の自主性を高めつつ両国の協力体制をさらに合理的なものとするため、日米安全保障条約の改定に関する協議を進めつつありますが、このことは、わが国の安全と繁栄とを確保するのみならず、自由主義陣営の結束を強化し、世界平和の確立に資するものとの確信に基づくものでありまして、過般の各国訪問により、更にその確信を深めた次第であります。
過日のフルシチョフ・ソ連首相の訪米によつて、国際間の諸問題を話し合いによつて解決しようという雰囲気が一段と醸成されましたことは、まことに画期的なことであります。私は、このような両陣営の話し合いによつて国際間の懸案が解決され、世界平和を一歩一歩前進させることを衷心より願うものであります。
本臨時国会の開会に際し、わが国の当面する外交上の諸問題とこれに対処する所信を明らかにいたしたいと存じます。
私は本年九月初旬国連総会に出席のため渡米いたしたのでありますが、略々時を同じくしてフルシチョフ・ソ連首相の訪米が行われましたので、その直後に親しくハーター米国務長官とも会談し国際情勢全般とともに今後の日米両国の関係につきましても同長官と隔意ない意見の交換を行うことが出来ました。
すでに本年初頭の通常国会に際しても明らかにいたしました如く、私はわが外交の基調としてあくまで平和外交を旨とし、このため国際問題はすべて平和的手段によつてのみ解決さるべきことを主張してまいつたのでありますが、このほど米ソ両国首脳の話合いにおいて国際問題の平和的解決という原則が一応確認されましたことは政府といたしましても歓迎するところであります。
今回の両国首脳の話合いの結果を見まするに問題は主として欧州問題、しかもその重点はベルリンの危機回避におかれた模様であり、期限付き条件の下における交渉というような事態は一応回避されましたが、すべては今後に予想される外相会議なり、巨頭会談なり、長期にわたる折衝の結果にかかるものと考えるのであります。
軍縮問題に関しましても、最近国連において英国及びソ連より全面的な軍縮案が提出される等軍縮を通ずる緊張緩和の新たな努力を行おうとする傾向が見られますことは、まことに喜ばしいことであります。わが国といたしましては、多年主張しつづけてきた核実験中止協定の早期締結を最も重要視するものでありまして、これが今後の全面的軍縮問題解決の契機となることを願うものであります。
われわれはこれら東西間の話合いが今後逐次具体的成果を見ることを希望し、これがために凡ゆる努力が払わるべきことを期待するものであります。その際自由民主主義諸国といたしましては、ますますその結束を強固にして些かのゆるぎない立場に立ち、共産陣営との公正かつ合理的な話合いに臨む体制をととのえることが最も肝要であり、今後長期にわたる忍耐強い交渉を行うことによつて初めていわゆる「雪解け」も期待しうるものと考えるのであります。
次に今次国会において御審議を願いますヴィエトナムとの間の賠償協定及び借款に関する協定につき御説明いたします。
ヴィエトナム国政府は世界の約五十カ国よりヴィエトナムにおける唯一の正統政府として承認されており、一九五一年九月八日の桑港平和条約には、全ヴィエトナムを代表する正統政府としてこれに調印し、翌五二年六月十八日同条約批准書を寄託いたしました。これによつて、わが国はヴィエトナムに対し、平和条約第十四条に基く賠償支払いの義務を負うこととなつたのであります。その後、本件賠償に関する交渉は七カ年の長きにわたつて続けられ、幾多の紆余曲折を経ましたが、漸く本年五月調印をみるに至つた次第であります。
本賠償協定は、わが国が条約上賠償義務を負つているアジア諸国との間の賠償協定として最後のものでありますが、わが国が平和条約上の義務をできる限りすみやかに果しますことは、国際信義の上からも望ましいことであるとともに、他方この賠償の実施は、ヴィエトナムの経済建設と民生安定に寄与し、両国間の友好親善関係を強化し、政治、経済、通商、文化の各般にわたる両国間の協力を一層緊密にするものと確信いたすものであります。
次に当面の重要案件について御説明いたします。
政府は過去一年にわたり日米安全保障条約改定の交渉を行つてまいつたのでありますが、その要旨は既に国会におきましても累次にわたり御説明してまいつたところであります。すなわち、現行条約締結後七年を経過いたし、名実ともに独立国としての地歩を確保いたしましたわが国として、安全保障の分野における日米両国間の協力関係を、今日の事態によりよく適合せしめるとともに、国連憲章の精神に則りつつ、わが国の独立と安全とを確保し、両国の友好関係をさらに促進することを目的とするものであります。政府は次期通常国会において新条約の承認を求めるべく交渉の進捗を図つております。
日韓会談につきましては、本年八月十二日再開以来法的地位委員会と漁業委員会が開催されておりますが、政府といたしましては、過去における日韓両国間の複雑な経緯にかかわらず、相互の努力によつてすみやかに信頼感を確立し大局的見地から、諸懸案の公正かつ合理的な解決に努め、もつて日韓両国間の恒久的友好関係の基礎をきずきたいと念願いたしている次第であります。
また、釜山に抑留されている日本人漁夫の帰還問題につきましては、政府は引続き努力をしてまいりましたが、近くこれが実現に至るものと期待いたしております。
なお、在日朝鮮人の北鮮帰還問題につきましては、九月二十一日より帰還申請の受付を開始いたし、実施の段階に入らんとしております。わが国といたしましては、本件は個人の自由意思に基く帰還であるという基本方計を堅持しつつ、帰還が所期の如く円滑に実施されるよう万全を期しております。
国連におきましては、わが国は昨年一月以来安保理事会の非常任理事国として各種国際紛争の平和的解決のため公正かつ建設的な態度をもつて努力してまいりましたが、最近はラオス問題に関しその事態の平静化のため積極的な役割を果しましたことは各位の御承知のところであります。この非常任理事国の任期は本年末をもつて終了いたし、わが国は来年初頭より経済社会理事会の理事国として、世界の経済的、社会的発展を通じて国際平和を強化するという国連の事業に積極的に参加することになりました。私は今後ますます重きを加えるわが国の責任を自覚いたし、国連の平和建設事業に出来得る限りの協力をして行きたいと思うものであります。
すでに御承知の如くこのたびわが政府の招請に応えてガット総会が初めてジュネーヴを離れ、その第十五総会が東京において開催されておりますが、私はこの機会に、訪日する各国の関係大臣及び代表が親しくわが国の産業経済の実情を視察され、その認識を深められんことを期待するものであります。同時に今回の総会が契機となり多年懸案となつておりますわが国に対する貿易上の差別待遇撤廃の問題がすみやかに解決することを期待するものであります。
以上当面の諸問題に関し報告かたがた私の所信を明かにいたしました。各位の深い御理解と御支援とを要請する次第であります。
七月三日衆議院外務委員会における藤山外務大臣の外交問題に関する経過報告
本委員会の開催に際しまして私から第三十一回通常国会以降の主要な外交関係事項の経過について御報告いたします。
私は去る五月十三日サイゴンに赴き同地においてヴィエトナム共和国との賠償協定に調印いたしました。ヴィエトナム賠償に関しましては政府といたしましても既に屡々その所信を表明したところでありますが、元来ヴィエトナムは桑港平和条約の当事国としてこれを批准いたし、同条約に基いてわが国に対する賠償請求権を有するものであります。而してヴィエトナム共和国政府はヴィエトナム全体を代表する政府として自由諸国のほとんどすべてが承認している政府であり又わが国が正式の外交関係を維持しているものであります。今回同国政府との間に調印されました賠償協定は桑港条約に規定されたわが国の賠償義務を履行するための協定に他ならないのでありまして政府といたしましては右協定につき国会の十分な御審議を得る所存であります。
なお、先般ビルマ連邦政府より、日緬平和条約の再検討条項にもとづき、ビルマ連邦に対するわが国の賠償について再検討方を求めて参りました。政府といたしましては、ビルマに対する賠償額は、他と比較して均衡を失しているものとは考えておりませんが、何れにいたしましても先方のいい分をも十分聞いて見るという目的で最近ビルマ側と本件についての予備的話し合いを開始いたした次第であります。
私はヴィエトナムを訪問いたしました後カンボディア及びラオス政府の招きを受けてこれらの両国を訪れ、今後ともわが国との外交関係、経済関係を強化すべき方途につきまして、それぞれの政府首脳と懇談したのでありますが、特にカンボディアにおきましては、わが国と同国との間の経済協力協定の実施細目について合意に達しましたので、右に関する公文の交換を行いました。この結果さきに国会の御承認を得ました経済協力協定は近く東京で批准書の交換を行いました上で具体的実施の段階に入る次第であります。
五月末私は米国に赴いて世界各国の首相、外相等とともにダレス米国務長官の葬儀に参列いたしました。多年米国の国務長官として世界平和のために奔走された同長官の業績については敢て多言を要さぬところでありますが、私は特に同長官が今日の日米親善のために払われた絶大な努力と献身に対してここに敬意と追悼の念を新にするものであります。
次に在日朝鮮人の北鮮任意帰還問題につきましては、わが国といたしましては何人も自国に帰り、また、その欲するところに居住し移転しうるという国際的にも広く認められた基本的立場に基いてこれを行うとするものでありましてこの自由意思に基く任意帰還という原則は決して歪められてはならないのであります。この原則はさきに日本、北鮮両赤十字代表の間で妥結を見ました帰還取極の中に明確に規定せられているところであり、この規定の下に帰還業務が実施されることを期待し、かつ、確信いたすものであります。もとより、本件が実施されることはわが国の北鮮に対する従来の立場ないし関係に些かなりとも変更を齎すものではないのであります。
なお、韓国に抑留されております日本人漁夫の問題は、それが同胞の運命に関するものであり一日も忽にしえないことでありますので、政府は、その速かな釈放のためつとに赤十字国際委員会にあつせんを依頼いたしました。その後留守家族代表もジュネーヴに赴き、直接事情を委員会に訴え、その協力を求めた次第でありますが、政府は更に最近スイス駐在の奥村大使をしてわが政府及び国民が本件について抱いている強い希望と関心とを重ねて強調せしめ、その善処方申入れしめたのであります。幸い同委員会側におきましても本件に関し深い理解と同情とを示し、これら漁夫の早期釈放方に現在折角尽力中であります。
政府といたしましては、今後とも出来うる限り速かに釈放が実現されるよう内外世論の支持の下にあらゆる努力を続けてまいる所存であります。
次に安保条約改定問題について一言いたしたいと思います。本件改定の交渉は前回の国会終了後、米国側と更に約十回の会談を重ねました。改定新条約の構想中主要な点につきましては、既に過日総理大臣もその所信表明に際して明らかにされたところでありますが、今更にその要点を述べますれば、国連憲章との関係を規定すること、日米両国が政治的かつ経済的に共通の基盤に立ちその協力関係を促進すること、米国の日本防衛の義務を明かにすること、条約の運営に関してわが国の発言権を確立すること並びに新条約においてわが国の負うべき義務は憲法の範囲内なることを明かにすること等であります。
更に行政協定に関しましても、その締結当時よりの情勢の変化にかんがみ、所要の調整を行うべく目下折衝中であります。
もとより現行条約といえども今日までわが国の平和を守るという点において重要な役割りを果してきたのは事実でありますが、条約締結当時わが国の置かれていた客観情勢にその後相当の変化が生じておりますので、右に応じた所要の改定を行いますとともに今後の国際情勢の下においてわが国の平和と独立を確保し得る現実的な方途としての安全保障体制を規定せんとするのが今次改定交渉の趣旨であり、新条約の目的及び性格はあくまで平和の擁護と侵略に対する防衛に存するものであることをここに重ねて明らかにしておきたいと思います。
右改定交渉は必ずしも容易なものではなく、目下のところ未だ条文を最終的に確定する段階には至つておりませんが、米国はわが政府の主張に対し十分理解ある態度を示しており、遠からず妥結を見るものと考えております。
第二次大戦後十余年にわたる冷厳な世界情勢特に今日なおわが国周辺における政治上、軍事上の極めて不安定な情勢を考えますれば、平和を守る道は決して容易なものでなく、世界的にも又局地的にもつねに現実に即した平和への保障措置を積極的に講ずる要があると考えるのであります。
先般来ジュネーヴで開催されております東西外相会議も約一カ月余の討議を経ながら独逸統一問題及び欧州安全保障の問題等について双方の主張は依然として根本的に対立し結局何等の進展をも示しませんでした。よつてまず対象をベルリン問題に局限いたしましたものの、遂に何らの合意に至らぬまま休会に入り、近く会談は再開される模様でありますが、果して外相会談自体が何らか建設的な結論をうるに至るか否かはなお予断を許さぬところであります。
外相会議がその行詰りを打開し巨頭会談の開催を可能ならしめるとともに大国間に平和促進の為の有効適切な合意が成立いたしますことは最も望ましいところであります。しかしながら現状における東西間の対立は根本的な政治的信条の対立に由来するものでありますので、巨頭会談が開催されましても緊張の緩和が一夜にしてもたらされることは望み難いのでありますが、問題の解決が困難であるが故にこそ大国の首脳者による平和促進による努力が真剣に続けられることを希望するものであります。
以上、前回の国会以後の外交問題に関しその経過を御報告いたした次第であります。
議長閣下
貴下が第十四回国連総会議長に満場一致選挙されたことについて、わが代表団より心からお祝い申上げたいと思います。国連発足以来の貴下の国連に対する大なる貢献は、全加盟国代表の等しく認めるところでありますが、特にわが代表団は、国連加盟に当つて貴下のわが国に与えられた援助を忘れることができません。
私は、第十四総会のへき頭に当り、今こそ国際緊張の緩和と平和の増進のため一層真剣な努力を払わねばならないことを世界各国に訴えたいと存じます。
今日世界の平和を不安定にする最も大きい原因は、自由・共産両陣営の対立であります。この対立は、政治的信条の相違に基くものでありますが、これが相互の不信感によつて一層尖鋭化しているという事実を無視するわけにはいきません。
わが国の属する自由陣営は、自由と正義に基く民主的秩序の確立をもつて政治的信条とするものであり、世界の平和も、このような民主的秩序の上に築かれたものでなくてはならないとの立場を取つているのであります。共産陣営の唱える平和とわれわれの求める平和は、異なる性質のものであるかも知れません。しかしながら、基本的に相反する考え方を有する二つの陣営が現に併存しているという事実がある以上、平和維持を目的とするわれわれの努力は、両陣営が相互の不信感を解消しつつ対立を緩和するにあると存じます。そして、そのためにわれわれは、あらゆる機会を利用し、実行可能な具体的方策を見出さなければなりませんが、軍事科学の極度の発展によつて招来された原子兵器時代において、一歩誤ればわれわれの文明も、はたまた人類自体も破滅する危険に直面している今日、こうした努力の必要は、ますますその度合を高めているのであります。
具体的な緩和策を見出そうというからには、ただ言葉の上で平和を唱えるだけでは何の役にも立たないことは申すまでもありません。平和への意志が行為によつて裏付けられなければならないのであります。そうした行為の指針として、国際連合憲章は国際紛争の平和的解決の原則をあげております。国際紛争を武力の脅威または行使によらないで、話合いにより平和的に解決することは、単に加盟国の義務に止まらず、今日世界の共同社会の一員として当然遵守すべきものであります。これと同じことは、国際関係において、相手国の政治的立場を互いに尊重することについても言えるのであります。自国の利益または勢力を伸長する目的の下に他国に対し直接間接に圧力を加え、あるいは干渉するというような行為は、厳に慎むことが必要であります。
以上申し述べたことに関連し、私は今回の米ソ両国最高首脳者の相互訪問を衷心から歓迎するものであります。両者が腹蔵ない意見の交換によつて互いに他に対する不信感を取除き、双方の納得する条件の下に東西間の諸問題を解決する糸口を見出すことによつて、国際緊張の緩和に貢献することを切望するものであります。そのことは、両国が特に指導的大国であるということから強調したいのであります。
東西対立の結果不幸にして生じた分裂国家の存在は重要な問題でありますが、わが国として特に指摘したいことは、わが国の近接地域にいくつかの分裂国家が依然として存在している事実であります。私は、これらの諸国が平和的、民主的過程を経てすみやかに統一を達成することを希望するものであります。これは、世界の平和に役立つと信ずるものであります。
東西両陣営間の対立と相互不信感は、また両者間の軍備競争という形で表われております。そして、その軍備競争は、さらにまた相互の不信感を増大し、これがさらに軍備競争を激化させるという悪循環を示しております。このような軍備競争は、人的および経済的資源の浪費であるばかりでなく、戦争の可能性を増大させるのであります。軍事科学の発達により核兵器等人類および文明の全面的破滅をもたらす兵器の出現した今日、私はこの感を一層深くするものであります。
私は、関係各国が相互不信感と軍備競争との悪循環を断ち切り、現状において実行可能な軍縮を行うことによつて信頼感を醸し出し、その上でこれを土台としてさらに次の軍縮措置に移るよう、軍縮交渉を極力推進することを関係各国に希望する次第であります。この点に関し、四カ国外相会議を契機として、新たに国連外に軍縮審議機関を設置することについて東西間に合意が成立したことは、関係各国の軍縮交渉推進の熱意として歓迎するものであります。私は、国連における軍縮交渉が一九五七年以来今日まで停滞していたことを極めて遺憾とすると同時に、新機関が新しい角度から軍縮問題を審議し、速やかに具体的成果を挙げることに全力を傾注すべきことを特に強く訴えたいと思います。軍縮は、主要大国間の合意が前提であることはいうまでもありませんが、同時に全加盟国の関心事でもあります。例えば、軍縮の実施に当つての有効な管理査察組織の設置は、国連および全加盟国の協力を不可欠の条件としておりますし、また近代兵器が関係当事国以外に与える影響のあることも事実であります。私は、新機関と国連との間に適切な関係が設定され、国連全加盟国の意向がこれに十分反映されるような措置が考慮されなければならないと考えます。
軍縮交渉今後の進展の契機となるべきものとしてわが代表団が特に強く期待するのは、核実験中止に関する協定の早期締結であります。わが国民および政府は、その体験に基く人道的見地から如何なる国の如何なる核実験にも反対してまいりましたが、この立場は、今後も一貫して変らないものであります。わが代表団は、かかる立場から核実験中止に関する協定を速やかに他の軍縮措置に優先して成立させるよう強く訴えてまいりました。わが国は、昨年の総会にオーストリアおよびスウェーデンと共にジュネーヴ核実験中止会議の成功を希望する趣旨の決議案を提出し、総会によつて採択されましたが、われわれのこの要望に応え、米、英、ソ三国代表が昨年来交渉を継続されてきた努力を多とするとともに、昨年末以来世界に核実験が行われなかつた事実を喜ぶものであります。同時に、両国首脳の相互訪間を契機として、少くともこの核実験中止交渉が速やかに妥結に至る道を開くことを切望致します。
国連が「公開外交」を通じ相互理解の増進による国際緊張の緩和に果した役割は、極めて大なるものがあります。国連はまた常駐代表間の接触や、事務総長の斡旋等による「静かな外交」を通じ平和の維持に顕著な役割を果してまいりました。国連の機構と機能は、平和維持のために今後ますますその重要性を増大するものと確信するものであります。今回国連がラオスの事態に対して迅速な措置をとつたことは、事態の平静化への第一歩として誠に適切であつたと信ずるものであります。なおまた、最近の著しい科学の発展に対応し、国連が昨年の総会以来大気圏外の平和利用に関する諸問題を取り上げたことは、時宜を得た措置でありました。本問題が今後ますます重要性を加えることを考えると、国連における関係諸国の協力が一層要望される次第であります。
他面国連は、東西対立という国際情勢の制約を受けて、本来の機能を十分に発揮し得なかつたことも認めざるを得ません。更にまた、国連が時によつては宣伝の場として利用される傾向が見られたことも認めざるを得ません。私は、国連が東西の対立を克服して真に平和維持機構となるよう、そしてまた諸問題の実際的、かつ建設的解決を計るために責任ある意見の交換の場となるよう国連の機構および機能の強化と有効な活用を計ることにつき加盟国が積極的に協力を行う必要のあることを強調したいと思います。この点に関し、私は事務総長の「年次報告序説」に述べられた種々の意見に原則として同意するものでありますが、さらに国連のプレゼンス、国連平和軍等についても研究を続けることが無意味でないと考えます。私は、またさらに一歩を進め、国連憲章をできるだけ速やかに改正することが国連を真に有効な平和維持機構とすることに役立つものと信じます。なんとなれば、現在の憲章は既に十四年前に起草されたものであり、その加盟国は著しく増加したのみならず、起草当時予見されなかつた多くの新事態が起つているからであります。憲章の改正を行うことは種々の困難を伴い、かなりの時日と忍耐を要すると思われます。それ故にこそ、私は、加盟国に対し憲章改正の事業に速やかに着手するよう呼びかけたいと思います。
以上私は、政治的、軍事的観点から平和の維持増進に関する希望を申し述べましたが、次に世界平和の裏付をする経済的、社会的発展の観点から所見を申し述べたいと存じます。
国連は、経済社会の分野において貴重な貢献を行つておりますが、なお多くの活動の余地が残されているのも事実であります。最近の世界経済において一番人目をひくことは、先進工業国と第一次産品の生産だけに依存する多くの低開発国との間の経済成長率の差がいよいよ開き、両グループの国の間の生活水準の隔たりが、ますます大きくなつている点であります。こうした傾向は、低開発国において依然として飢餓と疾病の支配、また教育と社会福祉制度の不足を意味し、これらは深刻な社会不安の原因となつているのであります。
こうした事態を改善しなければ、結局は世界全体の経済的、社会的発展が損われ、ひいては国際政治の安定が乱されるおそれがあるのであります。
従つて低開発国としては、その経済発展のため一層の努力を行い、また先進国としてもこれを助けることが緊急の必要となります。しかしながら、低開発国が、これを遂行するに当つての困難は、誠に大なるものがあります。比較的短期間にその工業化を達成したわが国としては、低開発国の当面する問題について深い同情と理解とを有するものであります。低開発国経済の多様化はこれらの国の経済成長達成の一つの方法でありますが、多様化に当つては、右に必要とする産業技術や経営能力はどのようにして確保するか、また必要な額の資本を如何に確保するかなどの大きな問題を急速に解決して初めて可能となるのであります。後進国は、これらの問題解決のために援助を必要とします。先進国は、また最大の援助を惜んではなりません。この場合、低開発国に対する援助は、どこまでも援助受入国の立場を尊重し、その希望を考慮したものであるべきで、いやしくも冷戦の具になるようなことがあつてはなりません。
低開発国の経済開発と共に今後の世界経済の発展にとり不可欠なものは、貿易の拡大であります。私は、この問題についてここではその一面のみについて申し述べるに止めたいと思います。最近地域的な貿易取極の動きが見られますが、こうした経済統合によつて地域内においては貿易の障害が除去されるわけであり、これは貿易拡大の見地から大いに注目に値するところであります。しかしながら、これらの経済統合は、万一偏狭な地域主義に堕して地域外諸国との間に摩擦を生ずるようなことがあれば、世界貿易拡大の見地から極めて遺憾なことであると考えますので、私は、こうして摩擦の生じないよう国連が調整の場としての役割を十分果すことを希望いたすものであります。
近年国連の各機関において人口の増加が経済的、社会的発展に及ぼす影響の問題が検討されております。私は、国連がさらに一歩を進めて、関係各国の希望するところにより経済開発に必要な技術者を含む人的資源を導入することに関連する基礎的諸問題について、調査研究を行うことを希望いたします。将来こうした調査研究の結果、移住の問題についても各国の理解が一層深められれば、単に経済開発に寄与するばかりでなく、関係各国の親善ならびに国際社会の平和の増進にも貢献するところ多大なものがあると考える次第であります。
わが代表団は、この総会に臨み、以上のような基本的態度の下にわが国の外交の基本原則である国連協力の実を挙げたいと思います。最後に、私は、この総会が貴議長の下に多大の成果を収めることを希望します。
(注) 全炉物理的不純物係数は、百分率で表され、かつ、すべての不純物のそれぞれの不純物のそれぞれについて、つぎの式を適用して算出した数値の和として定義される。ただし、Xは、不純物の百分率を示す。