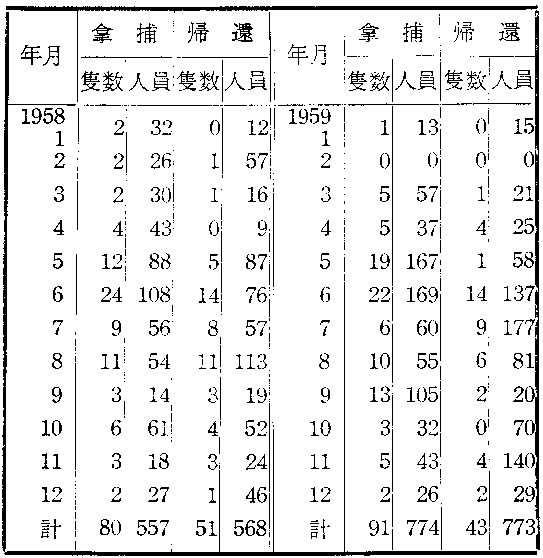
| ソ連および東欧関係 |
日ソ漁業問題に関しては、一九五七年二月から四月まで東京において、また翌五八年一月から五月までモスクワにおいて、北西太平洋日ソ漁業委員会の第一回および第二回会議が開催されたが、昨年一月十二日から再び東京で、同委員会第三回会議が開催された。
この第三回会議には日本側からは、藤田、坂村、新関の三委員の外、二十二名の随員が出席し、ソ連側からは、モイセーエフ、パーニン、フレストフの三委員の外、八名の随員が参加し、本会議を開催すること三十九回、科学技術小委員会を開催すること二十九回におよんで、諸問題に関する論議を重ねた。その間、両国委員間にしばしば非公式会談を開き、また会議末期においては、藤山外務大臣とフェドレンコ大使、および岸総理大臣とフェドレンコ大使の間で、またモスクワにおいては門脇大使とイシコフ大臣の間で、最も重要な問題であるさけ・ますの総漁獲量につき交渉を重ねた上で漸く双方妥結に達し、五月十三日百二十二日にわたる会議を終えた。
この会議においては、下記(1)に述べられているとおり、さけ・ますの年間総漁獲量を八万五千トンと決定した外、その他の諸問題についてもそれぞれ決定を採択したが、そのうち主要な問題の審議経過および結果は、概要下記のとおりである。
さけ・ます総漁獲量の決定は、さけ・ますの資源状態に関する評価とその年におけるさけ・ますの来遊に関する判断とを前提として審議されるので、まずその問題から始められたが、日本側では、一九五九年におけるさけ・ますの資源状態について、同年は豊漁年たる一九五七年程度あるいはそれを上廻るものと評価し、規制区域における日本側の漁獲量は十六万五千トンが適当であるとの見解を表明した。これにたいしソ連側は、一九五八年におけるソ連側の漁業実績が甚だ減少し、産卵河川への親魚の湖上および稚魚の降下が低下した点等からみて、一九五九年の資源状態は、比較的豊漁年であつた一九五七年に比し著しく悪化しており、一九五九年は低位豊漁年であるとなし、またこの資源の減少は日本の沖取漁業のためであるとの見解をとり、総魚獲量の決定は各種の問題を審議した後に行なわれるべきであるという態度を示した。この双方の態度に関連して、委員会は資源状態に関する審議を科学技術小委員会に付託し,小委員会は二十八回にわたる会議を重ねたが、双方の見解はほとんど一致するにいたらなかつた。
さらにその直後ソ連側は、次項に述べるような一定の水面と漁期を示した三つの操業可能区域の設定を提案したため、漁獲量の決定はいよいよ遅延したが、三月二十六日にいたつてソ連側は、一九五九年の規制区域内の漁獲量を五万トンと定めることを提議して来た。日本側は強くこれに反対し、委員会の非公式会談において、十三万トンとすることを提案したが、ソ連側は、日本側から規制措置に関し具体的提案があれば、漁獲量について修正提案を出す用意があるという態度を示して容易に譲らず、四月十四日にいたつて、わずかに六万トン案を提示した。日本側は、これを拒否するとともに、委員会の枠外においても交渉する必要を認め、藤山外務大臣からフェドレンコ大使にたいし、またモスクワにおいては門脇大使からイシコフ漁業部長にたいし、さらにまた岸総理大臣からもフェドレンコ大使にたいし、日本側の主張を申し入れて日ソ双方の提案の接近を図ることに務めた。ことに最終段階の五月十日には、日本側は九万トン案を提示したが、その後ソ連側は八万五千トン案をもつてこれに応え、結局五月十三日、八万五千トンで妥結した。
ソ連側は第三回会議においては、沿岸に禁漁区域を年々協議設定するという従来の方式とは著しく趣を異にし、三月六日、カムチャツカ東海岸および千島諸島の東方海上にさけ・ます漁業を行ないうる三区域を設定し、かつ、その区域ごとに漁業の始期および終期を定めるという趣旨の極端な制限案を提示してきた。
同案の範囲は、第一区については千島諸島(捉択島以北)の沿岸(相当の距岸距離をとつた上)から東方海上東経一六五度におよぶ水面を、第二区についてはカムチャツカ半島南半(北緯五一度-五四度間)の沿岸(距岸距離同上)から東方海上東経一七〇度に及ぶ水面を、また第三区はカムチャツカ北半(北緯五六度-五九度間)の沿岸(距岸距離同上)から東方海上東経一六九度におよぶ水面を定めるものであつた。
これにたいして日本側は、ソ連側の本件提案は従来沿岸に接近した場所に禁止区域が設けられてきた趣旨に矛盾すること、ソ連側指摘区域によればさけ・ます規制区域面積の八〇%以上が禁止区域となり、公海漁業自由の原則に反し、条約上の禁止区域設定の規定と合致せず、わが国の沖取漁業の存在を無視するものであること、およびソ連側提案の科学的基礎が納得できないことなどをあげて強く反対するとともに、日本側として認めうるものとしてカムチャツカ東北岸沖および北千島東海岸沖における距岸二〇海里の禁止区域および漁業終期を八月十五日とすることなどを提案した。
しかしソ連側は、前記三区域を若干拡大するとともに、右三区域の東方にさらに一区域を加えることおよび漁業の始期を定めないこと等を認める以外には、なんら譲歩の色を示さなかつた。これにたいし日本側は、北千島方面で魚群の通過する重要な海峡部につき従来の禁止区域の外にさらに拡大した区域を設けうべく、この部分は距岸五〇-六〇海里とすることも可能であることを示して種々交渉したが、ソ連側はその後、コマンドルスキー群島をはさむ南北約百海里の幅の魚類の通路と北千島東方沖の三角形をなす禁止区域の付加を最後案として主張し、その区域を緯度経度によつて示し、日本側がこれを考慮するならば、さけ・ます総漁獲量についても再考の余地があることを述べた。このような経緯を経て、漸く最終段階にいたり、双方は大体前年と同様の禁止区域を認めるとともに、その外さらに東経一七〇度以西でコマンドルスキー群島をはさみ、沿岸禁止区域におよぶ水帯と、東経一六〇度線と北緯四八度線をもつて東および南から区画される北千島東方海域とを同様禁止区域とすることにより妥結することとなつた。
べにざけの漁獲上考慮すべき保存措置としては、これまで一定区域における漁期の制限、網目の大きさの増大、若年魚の混獲制限などが問題とされたが、ソ連側は第三回会議においては、前項で述べたように、まずさけ・ますの操業可能区域を特定し、その各区域における漁業の始期と終期とを定める案において、すでにべにざけの漁獲制限をも考慮したのであつた。さらに三月七日その審議に際しては、ソ連側はべにざけの漁獲量を一万トンとし、東経一六五度以東でその七五%を漁獲すれば直ちにその線以西に移動する案を提示した。またその後においては、母船の操業区域における使用網の網目につき、一九五九年の漁期始めから七月十日まで、七二ミリ・メートル未満の網目の網の使用を禁じ、その以後漁期の終りまで東経一六五度以西において、六〇ミリ・メートルの網を五〇%認めること、ならびにべにざけについては、体重一・八キロ未満のもの(なおしろざけについては二キロ未満とする)の漁獲を許容しないこととし、その未満のものの混獲は、一揚網ごとに尾数で一〇%以下を許容することなどの提案を行なつて来た。
以上の諸点につき、日本側としては、漁業の実状から種々反対を表明して交渉を続けたが、漸く五月八日左記の諸点について合意が成立した。
(イ) 網目については、日本側は声明により、日本政府は一九五九年において、母船付属漁船に六五ミリ・メートルの網目の流網を総数で千反以上使用せしめる方針をとること、一九六〇年において、規制区域の東半部(区域の西側の境界線は、一九五九年度調査研究の結果を考慮して定められる)の区域で、使用する流網の総数の二五%以上が六五ミリ・メートル以上の新らしい網目のものに取りかえられるべきことを明らかにした。
また一九六〇年以降四年以内に、以上の漁船によつて使用されている網を、より大きい網目のもの、すなわち六五ミリ・メートル以上のものをもつて、毎年総数の二五%ずつ取りかえらるべきことを明らかにした。
(ロ) べにざけ漁獲量については、日本側は声明により、一九五九年においてべにざけ漁獲制限に関し、漁業上および科学上の試験を実施すること、ならびに試験の実施に当り、べにざけの総漁獲量を八百万尾とし、このうち二百五十万尾を東経一六五度以西、北緯四八度以北の区域で漁獲する方針であることなどを明らかにした。
(ハ) べにざけ未成熟魚の混獲許容限度については、一九五九年にこの限度を定める問題につき、科学上および漁業上の調査を行ない、その結果を次回定例会議に審議のため提出することとした。
いわゆるはえ縄と称せられる釣漁具による漁業については、ソ連側は、これが大量の未成熟魚を漁獲し、多くの損傷魚を発生する漁具であるとして、かねてその使用の禁止を主張しており、また流網の細い糸が魚体を損傷するとして、これを太くする必要があることをも主張してきたが、第三回会議においてもソ連側は同様の主張をもつてそれぞれ案を提示して来た。
これにたいし日本側も対策を示してソ連側と審議を行ない、概要次のような点で合意を見ることとなつた。
(イ) 釣漁具については、日本側は一九五九年においても規制区域内で釣漁業を行なわず、また規制区域外においては、主として沿岸零細漁民にこの漁業を許可する方針であり、かつこの漁業の拡大は望ましくないという立場をとる。なおこの漁具による損傷を少なくする目的で、業者および団体にたいし、必要な措置をとるようにしょうようする。
両国はこの問題につき必要な調査研究を行ない、その結果を次回定例会議に審議のため提出することとした。
(ロ) 網糸の太さについては、委員会の決定によつて、現在使用されているもの(〇・五八九-〇・八二二ミリ・メートル)より太くすることが望ましいことを認め、また具体的太さの問題について漁業上および科学上の追加的調査研究を行なう必要があることを認めた。
にしん群の減少にかんがみ、ソ連側は第三回会議において、一九五九-一九六三年までの五カ年間、樺太、北海道にしんの分布区域、すなわち北海道沿岸、樺太南西岸および西岸、国後島近辺でのにしんの全面禁漁を提案し、日本側はこれに反対して審議を続けたが、結局、日ソ双方が自国のとるべき措置について、それぞれ次の趣旨の声明をすることとなつた。
(イ) 日本側は一九五九年以降三年間、北海道のオホーツク海沿岸および日本海沿岸における五カ所の代表的にしん産卵区域(海岸線総延長約五〇-七五キロ)に調査区域を設け、精密調査を行ない、漁獲の行なわれる区域と行なわれない区域とについて、産卵密度、産卵量および卵の死亡率、その他の調査、考察を行なう。
(ロ) ソ連側は樺太西岸(ゴルノザウォドスクーネウェリスク間五〇-六〇キロ)において、一九五九年以降全長一五キロにわたり、産卵にしんの禁漁区を設定し、かつ産卵にしんの分布、数量、産卵条件、各年級群の再生産などにつき調査研究する。
かに漁業の規制については、前年の第二回会議において、禁止区域、かに移動のための貫通路設定、母船数および製造凾数の制限、網の沈設期間および反数の制限など委員会の決定ないし声明によつてそれぞれ措置したが、第三回会議においては、ソ連側はさらに別の水域にも禁止区域を設定すること、操業区域を日本側とソ連側船団のために両分すること、許容漁獲量をさらに制限すること、その他詳細にわたり提案を行なつた。これにたいし、日本側は対案を示して交渉した結果、前会議におけると同様委員会の決定ないし声明によつて、諸種の措置についてソ連側と合意した。そのうち重要な措置は次のとおりである。
(イ) 一九五九年において、カムチャツカ西海岸の北緯五六度二〇分以北、五六度五五分以南を禁止区域とする。
(ロ) 母船数は日本側四隻、ソ連側六隻、漁獲量は日本側二八万凾(一凾半ポンド罐四八個)ソ連側二一万凾(一凾半ポンド罐九六個)とする。
(ハ) 操業区域は、日本側とソ連側とが相互に並行して操業し得るようそれぞれ緯度によつて区画を示した。
第三回会議においては以上の諸問題の外にも、さけ・ますの魚種別規制、害魚の影響、漁獲管理および漁業監視に関連する手続、学識経験者の交換などについて審議し、そのうち二、三の問題について決定ないし勧告案を採択した。かくて会議は前述のとおり五月十三日、両国の委員によつて議事録に署名を了した。
日ソ漁業委員会第三回会議においては、前回の会議と同様漁業に関する学識経験者の交換を行なうことについて勧告が採択されたので、両国政府間で、昨年六月末以来具体的な視察計画につき打合せを行なつた。ソ連側は八月一日、日本側学識経験者四名が八月十日から三週間の期間をもつてウスチ・ボリシェレツクおよびオゼルナヤ両コンビナートの河川流域における操業状況およびさけ・ますの産卵遡河条件の視察をすることに同意してきた。そこで日本側は相川水産庁調査研究部長の他外務省員一名、水産研究所および業界の専門家各一名より成る視察団を送ることとし、右の一行は八月九日第十五興南丸で函館発ナホトカに向かつた。翌十日ナホトカ到着後はソ連側の配慮により、八月三十一日まで予定どおりの視察を行ない、九月二日函館に帰着した。
他方、ソ連側からは、コルネイチューク・カムチャツカ魚類保護局長外三名からなる視察団が十一月十九日に来日し、北海道各地、長崎、大津、焼津、清水、東京その他の漁業施設、研究機関などを三週間にわたつて視察した上、十二月十二日帰国の途についた。
日ソ間に領土問題が未だ解決されず、南千島、歯舞、色丹がソ連の事実上の占領下にあるため、わが国の漁撈操業水域が戦前に比して著しく狭められたこと、本州北海道の沿岸および沖合の水産資源が近年とみに減少しつつあることなどの結果、北海道や本州の漁船は、漁業資源の多い樺太、千島、歯舞、色丹の岸(水産資源は陸岸に接近する程多くなる)に接近して操業せざるをえなくなつている。他方ソ連は一貫して領海十二海里説をとり、距岸十二海里周辺の海域で多数のわが国漁船を拿捕し、その乗組員を抑留するという措置に出ている。
領海三海里説を堅持するわが国としては、ソ連の十二海里説を承認するものではないが、事実上ソ連側との紛議を避けるため、わが国の漁業者にたいし十二海里以内に立入らぬよう国内指導を行なう一方、ソ連側にたいしては累次にわたり、拿捕漁船の返還、抑留漁夫の釈放を強く要求してきた。
ソ連は、わが国の漁船を拿捕した場合、これを千島、色丹島、樺太あるいは沿海州の基地に連行して取調べの上、領海侵犯、不法漁撈の容疑で起訴し、裁判の結果多くの漁船に対して船体、漁具、漁獲物の没収、船長または漁撈長に対して普通一年ないし三年の禁固刑を課している。起訴されない他の乗組員については通常わが海上保安庁巡視船の派遣を求めて洋上引渡しを行なつている。昨年中にソ連側に拿捕されたわが国漁船の数は、後掲の表のとおり一昨年に比して増加の傾向にある。
またソ連外務省は、一昨年十二月末口上書をもつて、わが国漁船の計画的かつ組織的なソ連領海侵犯の数が増加していると称し、今後拿捕漁船の乗組員および拿捕船舶の維持に要した経費補填のため、わが政府に請求書を提示し、また刑法上の責任を船長のみならず拿捕の際同乗の船主および漁撈長にもおよぼす旨を申し越した。これにたいしてわが政府は、在ソ門脇大使を通じ、昨年三月二十七日口上書をもつてソ連外務省にたいし、領海の範囲については、一九五八年ジュネーヴで開催された海洋法国際会議でなんら新らしい合意が得られなかつた現在、三海里が依然国際法上認められた規則であつて、三海里を越える海域をも領海とするソ連側の主張が有効でないのは当然であるが、日本政府としては、今回ソ連がとろうとしている措置は、たとえ国際法上認められた領海内における措置としても直ちに有効なものとは認めえない旨を通告した。
なおわが政府は、同時に右口上書の中でソ連による日本漁船拿捕事件に関する日ソ両国間の紛争の解決を国際司法裁判所に求める用意がある旨を述べ、また拿捕事件の発生を防止するため、かねてわが政府が行なつてきた北海道近海漁業に関する提案(その経緯については第三号一〇九頁近海漁業問題の項参照)をソ連側が検討し、すみやかに交渉開始に同意するよう要請した。その後ソ連側は、わが在ソ大使館を通じ、数回にわたり拿捕漁船乗組員の抑留経費を請求してきたが、わが政府はこれに応じていない。
終戦以来昨年末までソ連側に拿捕されたものは、海上保安庁の資料によれば、漁船八二九隻、乗組員七、二〇三名に上つており、そのうち六二八隻、七、一六一名(うち一名は遺骨)が帰還している。したがつて、二〇一隻、四二名が未帰還であるが、右二〇一隻のうち一四隻は沈没または大破のため船体が放棄されており、結局一八七隻が今日なお抑留されている。また未帰還者四二名のうち一一名は死亡しているので、生存残留者は三一名である。
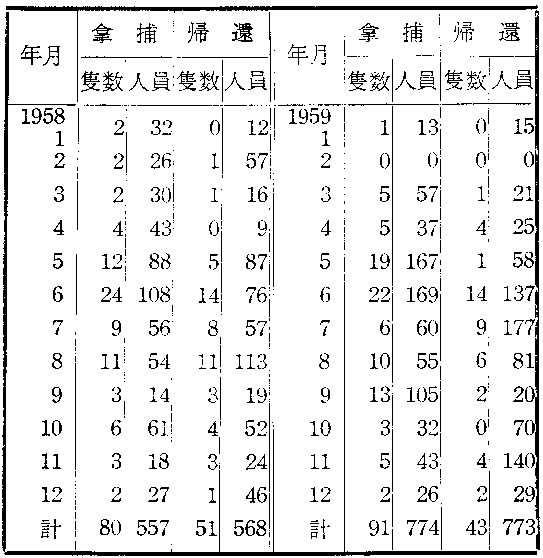
日ソ国交回復後再開された樺太よりの邦人引揚は、一九五七年同五八年の両年度に第十二次ないし第十六次に至る五回の配船が行なわれ、計二、〇〇〇人余(家族たる朝鮮人を含む)が帰国したが、昨年に入つてからは一月二十八日に一七二名(同上)九月二十五日五八名(同上)引取りのためそれぞれ真岡(ホルムスク港)へ配船した。
日ソ共同宣言第五項に基づいて、ソ連政府へ調査方を依頼してある消息不明の邦人は一昨年二月現在で七七六九名となつていた。その後わが政府が入手した資料によつてこれを整理した結果、右のうち二、〇八九名については状況が判明したのでこれを削除し、また新たに三六二名がソ連領に連行されていることが明らかになつたので、これらの人々の氏名を追加した。かくして差引調査依頼の対象は六、〇四二名となつたので、六月十二日わが国の在ソ大使館を通じて関係資料をソ連側へ提供し、調査結果の通報方を依頼した。これにたいしてソ連赤十字社より、ソ連領内で死亡した邦人として十一月二日に六〇二名、十二月三十日に一二八〇名の名簿がそれぞれ提供された。
日ソ国交回復以来、ソ連政府は日ソ両国間の直接航空路の開設に関し、折にふれわが国の態度を非公式に打診してきたが、昨年三月二十二日に至り、在京ソ連大使館アディルハーエフ参事官は金山欧亜局長を来訪して正式に本件の申入れを行なつて来た。しかし航空路を東京-モスクワ間とするわが国の主張と、これを日本の一地点とハバロフスク間とするソ連側の主張が対立したので、わが国は、その後同年十月二日付口上書をもつて、再度東京-モスクワ間に航空路を開設することにつきソ連側の同意を求めたが、以来なんら正式回答に接しなかつた。
なおこれとは別にソ連航空機の本邦不定期乗入れに関しては、わが政府は一昨年度航行の安全と技術援助のため邦人誘導員が同乗することを条件としてこれを許可したので、レニングラード交響楽団員の往復の輸送およびモスクワ芸術座員の往路の輸送計三回の乗入れが行なわれた。
昨年度においては、まず右モスクワ芸術座員の帰国のためTU一〇四A機が前回と同一の条件で一月十一日乗入れを行ない、即日出発した。さらに本邦公演のモイセイエフ・ソ連国立舞踊団員の輸送のため同一の条件でソ連TU一〇四ジェット機二機の乗入れが許可されたので、団員の本邦入国のために九月十三日乗入れを行なつて即日出発し、ついで同団員帰国のために十一月四日乗入れを行ない、翌五日出発した。
ソ連政府は軍縮、核兵器の不使用および実験の停止、核武装禁止地帯の設定等重要国際問題に関し、一九五七年末のいわゆるブルガーニン書簡以来、各国にたいして積極的にその主張の実現方を呼び掛けてきた。昨年においてその警告外交の一環として在京ソ連大使館スズダレフ公使参事官が五月四日、金山欧亜局長を来訪し、わが国内における核武装問題、極東非原水兵器武装地帯の設置、中立問題等を含む次のとおりの長文の口上書を提出し、わが政府の説明を要請した。
ソヴィエト政府は、一九五八年五月十五日付および六月十六日付大使館口上書において日本国政府に対し、核兵器および同兵器の目的地への輸送手段(飛行機、ロケットおよびその他)の日本領域への持込みに関する日本の新聞および政治家の発言が事実に適応するや否やにつき説明を要請した。
遺憾ながら、現在まで日本国政府は、上記の口上書において提起した諸問題に対して明確な回答を与えていない。しかしながら、日本国領域内に核兵器の存することは、極東における戦争の危険の新たな源泉となるが故に、日本国内における核兵器の配置は、ソヴィエト連邦において不安を招来せざるをえず、ソヴィエト連邦がこれを看過することができないことは判りきつたことである。
次に、日本国政府が日本国内米軍基地への核兵器および同兵器の目的地への輸送手段持込みの事実に関する多数の報道の打消を差控えていることが注意を惹く。それどころか、日本の公的人物は国会および公衆の面前における発言中において、日本に駐留する米国軍隊の原子および水素兵器による装備を正当化しようと試みている。それのみならず、近来、日本国為政者は日本国軍隊の核・ロケット兵器装備を事前に決定し、日本の原子装備の合法化をかちえようとする試みとしかみられない言明を行なつている。
日本国首相岸氏は、最近国会において発言し、日本の原子武装計画になんらかの法律的裏付の外観を与えんとして、日本国憲法を引合にさえだすにいたつた。日本国防衛庁長官伊能氏は、参議院予算委員会において、日本国軍隊は小口径の核兵器、たとえば核弾頭をもつ「オネスト・ジョン」ロケットのごときものをもつ意図がある旨を述べた。
かくして、以前の言明、とくにソ連政府あての一九五八年五月十七日付日本国政府口上書に述べられている言明、すなわち「日本国政府自身は、核兵器による装備を行なつておらず、また、日本国内への核兵器持込みを認めていない」との言明に反し、今や多数の事実は、日本国政府が、第一に、日本国領域に駐留する米国軍隊の核兵器による装備を奨励し、また第二に、日本国軍隊をかかる兵器で装備せしめようとする措置をとつていることを物語つている。
ソヴィエト政府は、もちろん、日本国政府にたいして、憲法をいかに解釈するか、または日本を第三国、すなわち現在の場合では米国と結びつけるいかなる義務を負うべきかという忠告を与えようなどとは決して考えていない。しかしながら、事一度日本国の領域内における核・ロケット兵器の配置およびこの種の兵器による日本国軍の装備に関する以上、前記の諸措置は、日本と隣接する諸国家の安全上の利益に抵触せざるをえない。日本の原子装備は、世界のさらにまた一つの地域、すなわち極東における核武装競争を誘致することとなるべく、それは「戦争瀬戸際」政策を実施する諸国家によつて、危機を設けるために利用されるであろう。また、日本の核兵器装備およびその領域内における外国の原子・ロケット基地の設置は、ソヴィエト政府にたいし、ソ連極東の安全上の利益が命ずる一切の措置をとることを必要ならしめるであろう。われわれは、日本と隣接する他の諸国も、日本の島々が米国の原子基地化する事実および日本国軍の諸種の大量殺戮兵器による装備にたいして無関心のままでいるわけにはゆかないであろう。
ソヴィエト政府は、日本国政府において、日本の原子装備が日本の国家とその国民自身のためにもたらす極めて重大な結果を、妥当に考慮するよう期待したい。人類史上最初に原子兵器の破壊的作用の悲劇を自ら体験した日本国民は、比較的小さな領土と高度の人口密度をもつ日本の原子・ロケット装備競争に参加することが何を意味するかを明確に知つているはずである。世界の諸地域における軍事ブロックの主たる組織者である国家のロケット・熱核兵器基地を日本国領域内に設置することは、国民の意志に反して、日本をロケット・原子戦争へ自動的に引きこむ結果となりうる。
日ソ間に今日まで平和条約が締結されていないこと、および、日本の無条件降伏文書に署名した大国としてのソ連邦は、日本の発展が極東および全世界における平和の確保を脅威するがごときことのないように配慮する特別の理由をもつていることを考慮し、ソヴィエト政府は、原子戦争準備へ日本を引きいれんとする日本国民にとつてゆゆしい結果を内蔵する措置について、日本国政府にたいし適時に警告することを自己の義務と考える。
ソヴィエト政府は、日本国の安全の確保は、日本の原子武装化の道にあるのではなく、その領域内の外国軍事基地を撤廃する道、また日本国が中立政策を実施する道にあるとの自己の確信をすでに繰りかえし表明してきた。
ソヴィエト政府は、日本国の永世中立の尊重と遵守とを保障する用意があることをすでに声明してきたが、今ここに重ねてこれを確認する。この目的のために、ソヴィエト連邦と日本国との間に、あるいはソヴィエト連邦、中華人民共和国および日本国との間に適当な条約を締結する問題について日本国政府と討議することができよう。またソヴィエト連邦、中華人民共和国、日本国、米国ならびにアジアおよび太平洋地域のその他の関係諸国を加盟せしめて、日本国中立の集団保障に関する多数国条約の締結問題を討議することもできよう。もし日本国においてその中立が国際連合によつて保障されるべき旨の希望を表明するならば、ソヴィエト政府としては、本問題のこのような解決をも歓迎するだろう。
右とともに、ソヴィエト政府は、極東および全太平洋地域に平和地帯、まず第一に非原水兵器武装地帯を設置することが極東における平和強化上の利益に、したがつて日本国自身および極東のその他諸国の安全強化上の利益に合致するものと考える。ソヴィエト連邦政府は、極東および全太平洋地域にこのような平和地帯を設置することに極力協力する用意がある。平和地帯の設置に日本が参加することは、極東および全世界における平和強化の事業に立派な貢献となるべきことは疑いがない。
ソヴィエト政府は、日本国政府がこの口上書に記述されている見解を慎重に研究され、日本国軍の原水兵器装備問題ならびに日本国領域内米国軍事基地への核兵器持込問題に関する自己の立場について必要な説明を与えられるべきことを期待する。
ソ連政府の右口上書にたいするわが政府の回答として、五月十五日山田外務次官は、フェドレンコ在京ソ連大使を招致し、次のとおりの口上書を手交してわが政府の立場を明らかにした。
一国の国防問題は、その国が自主的に決定すべきものであつて、他国の介入が許さるべきものではない。ソ連の口上書は、在日米軍の核兵器持込みおよび日本国自衛隊の核武装を問題としているが、日本国政府は、周知のとおり独自の立場からその政策として自ら核武装せず、また核兵器の国内持込みを認めないとの態度をとつているのであつて、日本国政府としては、この態度に関連しソヴィエト連邦政府の容喙ないし警告を受くべき筋合ではないと考えている。
口上書において、ソヴィエト連邦政府は極東および全太平洋地域に非核武装地帯を設置すべしとの提案をしているが、核兵器問題は軍縮全般に関連する問題であり、かつこの問題の解決に最大にして直接の責任を有しているのは、核兵器を所有する大国であることにつきソヴィエト連邦政府の注意を喚起したい。過去において原爆の惨禍を体験した日本国民は、世界の平和と安全のため、関係国間の合意により軍縮全般に関連しすみやかに核兵器の全面的禁止が実現せられることを衷心より念願し、国際連合等を通じてこれに関するあらゆる努力を続けてきた。今、ソヴィエト連邦政府が自国の強大なる核武装を維持しつつ、非核武装地帯を設置すべしとの提案を行なつていることは、この大国の責任を他に転嫁する態度といわざるを得ない。もし核兵器全面禁止に至る道程としてなすべきことがあるとすれば、まず査察制度を伴う実験禁止を手始めとし、漸次大国がかかる大量殺人兵器の生産、貯蔵および使用を不可能ならしめるよう努力することこそ肝要である。
客年十二月二日ソヴィエト連邦外務大臣より門脇駐ソ大使に手交された覚書は、随所において、現在行なわれている日米安全保障条約の改定に関する交渉は、日本の「侵略的軍事ブロック」への参加、日本の武装兵力の海外への派遣、日本国憲法の破壊等を目的とするものであるとしている。かくの如きは、日米安全保障条約が全く防禦的な内容と性格のものである事実を故意に無視したものといわざるを得ない。改めて申すまでもなく、日米安全保障条約は、日本国がその有する固有の自衛権に基づき自らの安全を守ろうとする自主的かつ純粋に防衛的性格のものであり、他国よりの侵略のない限り、第三国にたいして発動され得ず、したがつて如何なる意味においても他国に脅威を与える如きものではあり得ない。
世界恒久平和のため民主主義による秩序の維持とその確立を国是とするわが国は、窮局において世界の平和と安全が国際連合の手により全面的に確保されることを衷心希望し、これが強化のために全幅の協力を約するものである。しかしながら国際連合が完全にその機能と責任を果し得るに至るまでの間、わが国としては、国際連合憲章の下においてまず自らの安全を図る道を求め、かつ平和維持に寄与するための措置を講ぜんとすることは当然である。
ソヴィエト連邦政府は、また口上書において、日本国が自国の安全を求める手段として中立政策に転移すべきことを勧奨している。すでに指摘せるごとく自国がその安全を保持する手段として如何なる外交政策をとるべきやは、その国民が自主的に決定すべき問題である。ソヴィエト連邦の勧奨する中立の諸方策は、日本が自らの安全保障のため選んだ基本的立場と背馳するものであり、日本国の受け入れ難いところである。ソヴィエト連邦は一方において他国に中立を勧奨しながら、他方において独自の中立政策を堅持せんとする国を強く非難している。さらにわれわれはソヴィエト連邦を当事者とする不侵略条約ないし中立条約が過去において如何なる結末になつたかという歴史的な事実にも無関心たり得ない。
また口上書において、ソヴィエト連邦政府は、日ソ間に今日まで平和条約が締結されていないことおよびソヴィエト連邦が降伏文書に署名したことを口実として、あたかも日本国が自ら決定すべき問題につき警告を発する特別の立場にあるが如きことを述べている。不幸にして平和条約は領土問題未解決のために締結されていないがすでに日ソ共同宣言により戦争状態は終結し、日ソ両国が平和的にして正常な国交関係にあることは周知の事実である。しかるに今日、この明らかなる事実を無視し、あたかも内政干渉を正当化せんとするが如き見解がソヴィエト連邦政府により示されたことは甚だ遺憾であつて、日本国民は、かくの如き態度を容認し得るものでないことを明らかにしたい。
わが国とハンガリー、ルーマニアおよびブルガリアとの外交関係は、今次大戦後杜絶していたが、わが国は、昨年八月ハンガリーと、同年九月ルーマニアおよびブルガリアとそれぞれ国交を回復した。
ハンガリー、ルーマニアおよびブルガリアの三国は、第二次大戦に際して枢軸側に立つたが、大戦末期ハンガリーの敗戦によつてわが国と同国との外交関係は杜絶し、またルーマニアは一九四四年九月連合国と休戦して翌十月わが国との国交を断絶し、ブルガリアも同年十月連合国と休戦して、翌十一月わが国との国交を断絶した。
一九五六年五月、ハンガリー側よりユーゴースラヴィア駐在広瀬公使を通じて、国交回復に関するわが国の態度を打診して来たのをはじめとし、ルーマニアおよびブルガリアよりもわが国の在外公館を通じ国交回復の申入れがあり、さらに一昨年二月、ハンガリーより重ねて復交申入れがあつた。
わが国はすでにソヴィエト連邦、ポーランドおよびチェッコスロヴァキア等と国交を回復しており、またわが国の外交方針としてもできるだけ多くの国と外交関係を結ぶことが望ましいので、政府はハンガリー、ルーマニアおよびブルガリアとの外交関係を回復することに決定し、昨年三月チェッコスロヴァキア駐在木村大使をしてハンガリーと、同年四月ポーランド駐在太田大使をしてルーマニアおよびブルガリアと、それぞれ下交渉を行なわしめた後、プラーグおよびワルシャワで正式にこれら三国との国交回復交渉を開始した。
ハンガリーとの交渉は、同年七月末からプラーグにおいて木村大使とチェッコスロヴァキア駐在のハンガリー大使との間で行なわれたが、わが国とハンガリーとの間には外交関係回復に先立つて特に解決を要するような問題もなかつたので、交渉は短期間で妥結し、八月二十九日プラーグにおいて木村大使とマリヤイ・ハンガリー大使との間で、公文交換の日から両国の外交関係を回復し相互に遅滞なく公使を交換するという趣旨の公文が交換された。また同時に、戦前両国間に締結された条約および協定はすべて失効したことを確認し、かつ、両国は両国間の通商に関する協定締結の交渉を行なう用意がある旨を述べた公文が交換された。
ルーマニアおよびブルガリアとの交渉は、同じく七月末からワルシャワにおいて太田大使とポーランド駐在のルーマニア大使およびブルガリア大使との間で、それぞれ交渉が行なわれたが、ハンガリーと同じくこれら二国とわが国との間に外交関係を回復するに際してとくに解決を要する問題もなく、交渉は短期間に妥結した。かくてルーマニアについては九月一日太田大使とプラポルゲスク・ルーマニア大使との間で、ブルガリアについては同月十二日太田大使とボエフ・ブルガリア大使との間で、それぞれ、公文交換の日から外交関係を回復し相互に遅滞なく公使を交換するという趣旨の公文、および、戦前両国間に締結された条約および協定はすべて失効したことを確認するという趣旨の公文が交換された。