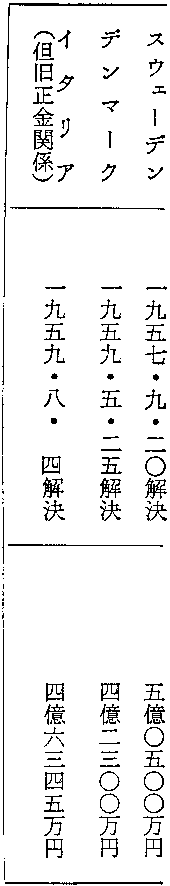
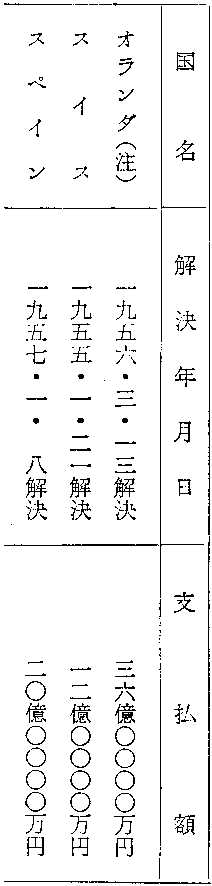
| 西欧関係 |
西欧大陸諸国は、米国および英国とならんで自由主義陣営の中核であり、また東西陣営の接触面として国際政治の上に極めて重要な地位を占めている。
最近これら諸国は、相互の協力関係強化することにより、米ソ二大国に比肩する第三広域圏の樹立をめざしていわゆる欧州統合化の動きを着々とすすめており、その経済力の充実と相俟つて、国際社会における発言力は著しく重要性を増すに至つた。
これら諸国との国交は、わが国の対外政策の上につねに重要な意義をもつてきたのであるが、ことに近年わが国とこれら諸国との関係は、ひとしく自由主義諸国の一員であるという共通の基盤の上に、政治、経済、文化その他各種の領域でますます緊密となつている。
昨年末現在わが国と西欧諸国との間に結ばれている主要な条約ないし協定としては、フランス、イタリアおよびドイツの三カ国との文化協定、ギリシャ、スペイン、スイス、スウェーデン、デンマーク、オランダおよびノールウェーの七カ国との通商航海条約、スウェーデン等北欧三カ国との租税条約(別項参照)、オランダ等七カ国との航空協定(別項参照)、ドイツ、フランス、イタリア、ギリシャ、オランダ、ベルギー、スウェーデン、デンマーク、ノールウェー、ルクセンブルグ、スイスおよびオーストリアの十二カ国との査証相互免除取極をあげることができる。
西欧大陸諸国とわが国との間の要人の往来も著しく頻繁となつているが、ことに昨年度は岸総理大臣がドイツ、オーストリア、イタリア、ヴァチカンおよびフランスの各国を訪問することにより、これら諸国との親善関係の増進に大きな成果を収めた(別項参照)。
わが国は一九五三年二月以来、オランダ、スウェーデン、ノールウェー、デンマーク、フランスおよびスイスの各国と航空協定を締結しているが、昨年はさらにベルギーとの間にも同種の協定の交渉が妥結し、六月二十日東京において右協定の署名が行なわれた。この協定は批准をまつて発効することになつている。また十二月二十一日にはフランスとの協定の付表(路線)を修正するための公文の交換が東京で行なわれた。
これらの協定によつて現在多数の欧州航空企業がわが国に乗り入れているが、近々日本航空も欧州乗り入れを実現する見込みであり、その手始めとして、本年二月二十二日日本航空とエール・フランスとの間に提携契約が締結された。
わが国は、一九五六年スウェーデンとの間に租税条約を締結したが、昨年二月十日には、ノールウェーとの間の同種条約が東京で署名されて同九月十五日発効し、また三月十日にはコペンハーゲンでデンマークとの間の同種条約が署名されて同四月二十四日発効した。
これらの条約は、所得に対する租税に関して二重課税の回避および脱税の防止を目的とするものであつて、この種の租税協定がわが国とこれら諸国との通商交通の促進に寄与するところが少くないものと期待されている。
わが政府は、核実検の禁止は政治上、軍事上その他あらゆる必要性に優先する人道上の要請であるという立場から、またわが国は核兵器の被害国として史上唯一のものであるという特殊な立場から、米国、英国およびソ連の行なう核実験に対してはその都度強くその中止を要請してきた(「わが外交の近況」第一号および第二号参照)。しかるに昨年初頭以来さらにフランスが核実験を行う気配が濃厚となつて来たので、昨年九月三日駐仏古垣大使を通じてフランス政府に対し、同国の核実験計画に対するわが国の深い関心を表明するとともに、同国がこの実験をあくまで強行する場合にはわが国は当然これに抗議すべき立場にある旨を申し入れた。
その後国際連合第十四総会は、十一月二十三日、わが国を含む五十一カ国の賛成によりフランスに対して核実験をさし控えるよう要請する旨の決議を採択した。
それにもかかわらずフランスは、本年二月十三日サハラにおいて核実験を実施したので、政府は、即日次の趣旨を古垣大使を通じてフランス政府に申し入れた。
「昨年の日本国政府の申し入れおよび国連総会の決議にもかかわらず、フランスが核実験を強行したことは、日本国政府の深く遺憾とするところである。日本国政府は、米国、英国およびソ連がすでに核実験を自発的に停止し、ジュネーブにおいてはこれら三国による核実験停止会議が進行しつつあるこの際、フランスが核実験を強行したことによつて、漸く生まれつつある核実験全面停止への全人類の願望が危くされることをおそれるものであり、ここに重ねてフランス政府が原子力を平和的目的のみに利用することに努力するよう強く希望するものである。」
オーストリア首相ユリウス・ラープ博士は、メツニック総理府新聞情報局長等随員三名を帯同し、昨年一月八日国賓として来日し、同月十七日離日した。同首相は、天皇陛下に謁見したほか岸総理大臣その他の政府首脳と会見し、また関西方面を視察した。同首相は岸総理大臣に対して近い将来にオーストリアを訪問するよう招請した。
ドイツ連邦共和国の、ベルリン市長(ベルリン州首相)ヴィリー・ブラント博士は、ベルリン州連邦問題大臣ギュンター・クライン博士を帯同し、わが外務省の招客として昨年二月十八日来日し、同二十一日まで滞日した。
岸内閣総理大臣は、昨年七月十六日から同二十三日までにわたり、ドイツ、オーストリア、イタリア、ヴァチカンおよびフランスの各国を訪問した。岸総理大臣は、これら各国の首脳者と会談し、丁度当時ジュネーヴで開催中であつた四国外相会議をめぐる欧州の情報や、中共および東南アジアを中心とするアジアの情報等について忌憚ない意見の交換を行つた。同総理大臣はまた、これら訪問国のうちでわが国に対しガット第三十五条を援用している国(オーストリアおよびフランス)に対しては、その早急な撤回を要請するとともに、欧州共同市場に加盟している国(ドイツ、イタリアおよびフランス)に対しては、共同市場が域外諸国に対する差別待遇によつて排他的性格のものにならないようにとの希望を表明した。各国訪問の概況はつぎのとおりである。
(イ) ドイツ訪問 岸総理大臣は七月十六、十七日の両日ドイツ連邦共和国を訪問し、ホイス大統領、アデナウアー首相、エアハルト経済相等と会見した。同総理大臣は、ドイツが今日なお不自然な分裂状態にあることに対するわが国民の同情の念を伝え、ドイツ統一問題が解決しなければ欧州および世界の緊張が真に緩和することはあり得ないという見解を表明した。両国首相は日独間の通商を拡大すること、低開発国援助のために日独が協力することの可能性等について話し合つたが、また岸総理大臣は、アデナウアー首相が近くわが国を訪問するよう招請し、アデナウアー首相はこれを快諾した。なおアデナウアー首相は本年三月下旬国賓として来日した。
(ロ) オーストリア訪問 岸総理大臣は、七月十七日から同十九日までオーストリアを訪問し、シェルフ大統領、ラープ首相、ピッターマン副首相、クライスキー外相等と会見した。両国首相は、すべての国際問題は国連憲章の精神にそつて平和的に解決されるべきであり、日墺両国政府は、このような方向に向つてその力を尽すべきであるという信念を表明した。また岸総理大臣から、オーストリアがわが国に対してガット第三十五条の援用を撤回するように要望したのに対し、ラープ首相は、この問題についてはオーストリアの経済的利害を考慮しながら十分慎重に好意的に検討したいと述べた。なお岸総理大臣のこの訪問は、かつてラープ首相が訪日したこと(別項参照)に対する答礼として行われたものである。
(ハ) イタリア訪問 岸総理大臣は、七月十九日から同二十一日までイタリアを訪問し、グロンキ大統領、セーニ首相、ペラ外相等と会見した。日伊両国首相は、両国の政治経済関係をより緊密化することについて話し合つたほか、東京のイタリア文化会館の開館、ローマの日本アカデミーの建設等を通じて文化交流を強化することについても意見を交換した。岸総理大臣はセーニ首相およびペラ外相が近くわが国を訪問するよう招請し、両氏はこれを快諾した。なお岸総理大臣の臨席の下に、ローマのエウル地区における日本通りの命名式およびわが国からの桜苗木の寄贈式が行なわれた。
(ニ) ヴァチカン訪問 岸総理大臣は七月二十一日ヴァチカン市国を訪問し、法王ヨハネス二十三世に謁見した。岸総理大臣から、戦後わが国が当面している諸問題について歴代の法王が理解と同情を示されたことに対し謝意を表したのに対し、法王はわが国の移民問題については今後とも協力を惜しまないと述べられた。
(ホ) フランス訪問 岸総理大臣は七月二十一日より同二十三日までフランスを訪問し、ドゴール大統領、ドブレ首相等と会見した。両国首相は、政治、経済、文化等の諸問題について話し合つたが、ことに通商関係については岸総理大臣から、フランスがわが国に対するガット第三十五条の援用を撤回するように要請した。ドブレ首相は、この要請をテーク・ノートし、この問題の検討について最善の注意を払うと述べた。岸総理大臣はまた、核兵器の禁止は唯一の原爆被害国たるわが国の国民的要望であるゆえんを説明し、早期に軍縮を実現することの必要を強調した。
第二次大戦の終了に伴い、世界各国からわが国に対して多数の請求権が提起された。これらの請求権を誠実に処理することはわが国の国際法上の義務であつて、これが長く懸案として残つていることはわが国の対外的信用にも由々しい影響をおよぼすものである。そこで政府としてはこれらの問題の解決に鋭意努力した結果、西欧諸国に関しては昨年末現在でほとんど全部解決するに至つた。これらの請求権は、サン・フランシスコ平和条約に基づくものと一般国際法に基づくものとに大別されるが、その処理の概況は次のとおりである。
連合国に属した西欧諸国は、平和条約第十四条(d)によつてわが国に対する賠償請求権を放棄したが、同条約第十五条(a)の規定により戦時中わが国内にあつた連合国財産の返還または補償を請求する権利をもつている。この種の返還ないし補償請求は、西欧諸国に関してはすでにほとんど全部解決した。
しかしフランスおよびオランダの二国は、その補償請求の一部についてわが国のとつた措置に満足しなかつたので、「日本国との平和条約第十五条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定」に基づきそれぞれ日仏財産委員会および日蘭財産委員会が設置され、この委員会が問題の最終的解決をはかることとなつた。
日仏財産委員会は、第三の委員(中立国委員)の任命について日仏両国政府が合意に達しないため、その構成が遅れていたが、その間両国政府の間にできるだけ話合によつて案件を解決しようとする努力が続けられた。その結果、本年二月八日に至りわずか一件を残し、他の案件全部が委員会の手続によらず円満解決するに至つた。日仏間の残りの一件および日蘭財産委員会付託の案件も遠からず解決するものと期待されている。
連合国に所属しなかつた西欧諸国(主として中立国)からは、戦時中これら諸国の政府および国民がわが国の軍事行動によつて蒙つた損害に対して、総額約四三九億円の補償請求が提起された。この請求権は、平和条約とは関係がなく一般国際法によつて処理されるのであるが、政府はこの問題を解決することがこれら諸国との友好関係回復の前提条件であることにかんがみ、もとよりわが国として補償すべきものは誠意をもつて補償するが、他面またわが国の負担は最少限度に止めるという方針で鋭意相手国と折衝を重ねた。その結果スイス、スペインおよびスウェーデンの請求権は先年解決したが、昨年五月二十五日にはデンマークの請求の解決に関する取極が署名され、即日効力を発生したので、これによつて西欧諸国のこの種請求権の主要なものはすべて解決するに至つた。
なお政府間の問題ではないが、「イタリア為替局」の旧横浜正金銀行に対する特別円勘定残高請求が久しく日伊間の懸案となつていたところ、昨年八月四日日伊両当事者間の直接交渉によつて円満に解決した。
昨年末までに解決した前記の諸請求権を表示すると次のようになる。
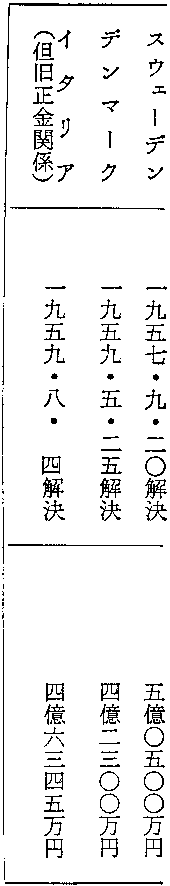 |
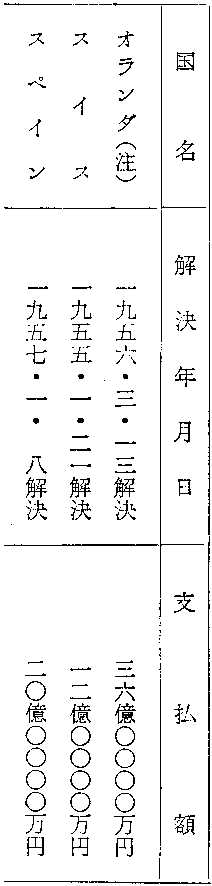 |
[注] オランダは旧連合国であるが、わが国は、平和条約調印に先立ち同国民に対する見舞金を自発的に提供する旨を約し、一九五六年その金額についてオランダ政府と合意に達したものである。