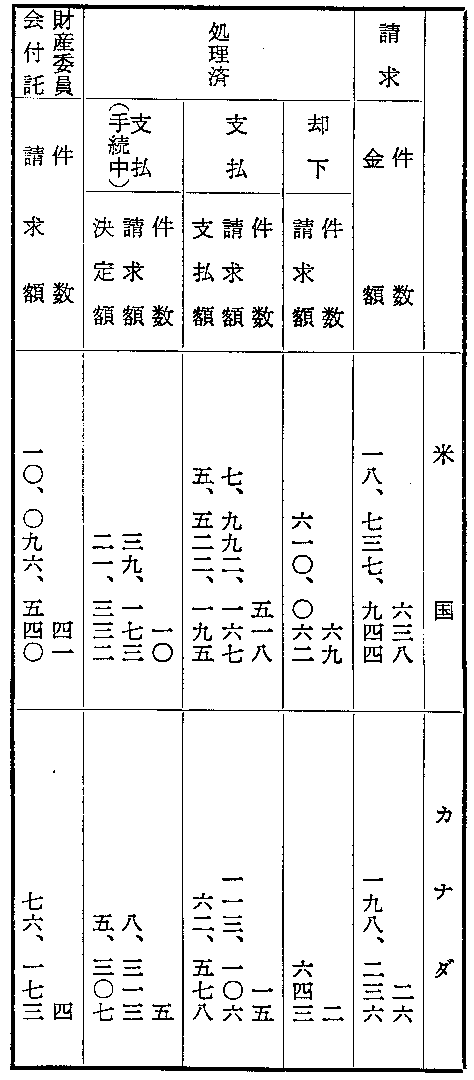
| 北米関係 |
安全保障に関する日米委員会は、(イ)駐留米軍の日本における配備、使用につき実行可能なかぎり協議すると同時に、日米安保条約に関して生ずる問題を検討し、(ロ)安保条約に基いてとられるすべての措置が国連憲章の原則に合致することを確保するため協議し、(ハ)これらの分野における日米両国の関係を両国の国民の必要と願望に適合するように今後調整することを考慮する、の三点を含み、広く日米間の安全保障問題の背景をなし、またこれに関連する諸事項を審議し、両政府間の相互理解と安全保障の分野における日米協力体制の強化に資する目的をもつ協議機関である(「わが外交の近況」第二号五六-五七頁参照)。換言すれば、安全保障に関する諸問題を政治、経済、国防等の観点よりハイ・レベルにおいて検討し、日米両国間の意志疎通と相互理解を深めるとともに、この分野における相互の立場の調整を図ることをその性格としており、委員会における審議の結果何らかの措置をとることとなつた場合は、両国はそれぞれ通常の手続によりこれを実施するものである。
本委員会は一昨年八月十六日以降現在までに六回にわたつて会合したが、その間とりあげられた主要問題は、(イ)在日米軍配備の協議、(ロ)在日米軍使用の協議、(ハ)防衛責任の承継、(ニ)極東の軍事情勢その他である。
参考までに第五回(四月十四日)および第六回(八月二十七日)委員会の会合に関する新聞発表を掲げれば左のとおりである。
安全保陣に関する日米委員会第五回会合に関する共同発表
(前略)
委員会は海上自衛隊および在日米海軍の施設の現況を検討し、今後の海上自衛隊の増強に伴う施設の使用について討議した。
防空問題に関し、近くレーダー・サイトが逐次日本側に返還される運びにあることが報告され、右に関連した諸問題が検討された。
委員会は、日本の安全保障に関連する最近の国際情勢、特に極東における最近の事態に関し、意見を交換した。
日本側委員より最近における駐留軍関係労務に関して存する諸問題を説明し、米側委員は、米国は、日本政府関係当局と協力しつつ、これらの問題に関し極力善処するよう努力を続ける旨、重ねて明かにした。
安全保障に関する日米委員会第六回会合に関する共同発表
(前略)
藤山外務大臣は左藤防衛庁長官、フエルト大将およびバーンズ中将が新たに本委員会に加わつたことに歓迎の意を表し、またハワイに常駐するフエルト大将が今後も都合のつく限り本委員会の会合に出席するよう要望した。フエルト大将は謝意を表し、今後もできる限り出席したき意向なる旨を述べた。
委員会は極東の一般軍事情勢に関して討議した。フエルト大将は特に日本の防衛と関連せしめつつその概説を行い、引続きこれについて意見が交換された。
委員会は次いで在日米軍の配備計画、自衛隊の装備の近代化促進の方途等について討議した。在日米軍の配備計画に関連し、施設および労務の所要量の見透しについても討議された。
現在在日米地上軍は戦斗部隊を保有せず、東京を中心として管理補給に当つている。海軍関係としては艦艇若干、艦隊、海兵航空隊および基地部隊が、横須賀、佐世保、厚木、岩国、追浜等に駐留し、第五空軍の主力と空軍関係の要員は三沢、横田、立川、入間川、板付、芦屋等に分駐し、東京都下府中にこれ等を統轄する司令部がある。
右在日米三軍の総数は約六万五千名といわれるが、今後共わが国の防衛力の整備と増強に応じ逐次減少することが予想される。
米軍に提供されている施設、区域の数はその後も減少傾向にある。昨年十二月一日現在の総件数は二九二件で、その中主要なもの(兵舎、飛行場、演習場等)は四四件に過ぎず、その他は事務所、倉庫、住宅等で占められている。
この件数を一昨年十二月一日現在の総件数四一四件に比べると一二二件の大幅な減少を示している。近く解除を予想される施設件数は約一〇件で、その中主要なものとしては東京造兵廠、東京陸軍病院等がある。
なお、平和条約発効以来の解除件数は四三九件(他に個人住宅六七五件)で、これを提供土地面積について比較すれば平和条約発効当初は民公有約二億坪、国有約二億一千万坪であつたものが、現在民公有約五千万坪、国有約九千八百万坪と著しく減少している。
対日平和条約第十五条(a)の規定に基き、日本政府は連合国人に対し、戦争中日本国内にあつて敵産管理等戦時特別措置に付せられた財産を返還し、またその財産が戦争の結果返還不能になり、または損害を蒙つた場合には、これを補償する義務を負つているが、右の中財産の返還については、返還可能なものはすでにほとんど返還を完了している。他方連合国財産の補償に関しては、関係法規の解釈、事実の認定、補償額の計算方法などについて、わが国と連合国側の間に見解の相違が存在する場合があり、それが両国間の話合によつても解決しないときには、「日本国との平和条約第十五条(a)に基いて生ずる紛争の解決に関する協定」に基き、両国政府がそれぞれ単独で任命する各一名の委員に両国政府の合意により任命される第三の委員を加えた三名の委員によつて構成される財産委員会に、最終的解決のため付託しうることになつている。右規定により日米財産委員会が設置せられ、すでに合計四十一件が同委員会に付託されているが、日米両国政府の合意によつて任命せられるべき第三の委員がまだ決定していないので、正式に審理を行う段階に達していない。なお日加間にも同様な財産委員会が設置せられ、合計四件が付託されているが同委員会も同じくまだ正式に発足する段階には至つていない。
昨年十一月末現在における連合国財産補償処理状況は左表のとおりである。
(金額単位円)
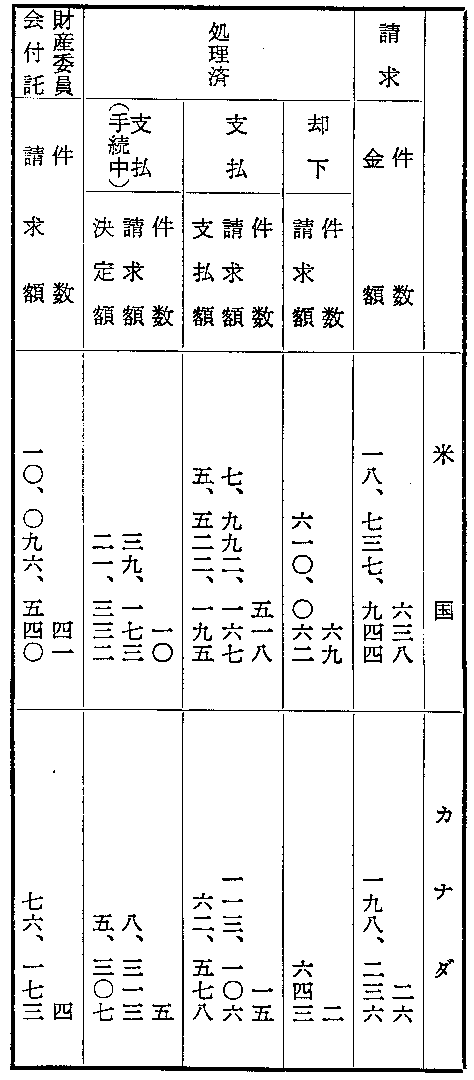
平和条約第十八条は、太平洋戦争前に生じた債務の支払についてのわが国の義務を規定している。この規定に基き日華事変中に生じたクレームとして米国から六件、カナダから三件が提出されている。これらのクレームはいずれも発生以来、相当の時日が経過しており、また証拠とすべきものが滅失しているものが少くなく、審査は困難を極めているが、わが政府としては平和条約の精神ならびに関係国との友好関係にかんがみ、これが解決のため関係当局者の間で鋭意検討中である。
一九五五年四月日米両国政府間に生産性向上計画に関する協定が締結され、爾来この計画の重要な事業として、海外諸国との技術交流が行われることとなつた。昨年においても、前年に引続きわが国の経営者、技術者、労働代表等が多数米国または西欧諸国に派遣されてこれら諸国の国内諸産業を視察したほか、米国からは専門家が招へいされ、また技術資料の提供をも受けてきた。
わが国における生産性向上計画の実施機関は財団法人日本生産性本部(会長足立正氏)であるが、これらの技術交流事業は前記政府間協定に基いて実施されるものであつて、資金は米国の対日技術援助資金と国内資金(政府および民間)から醵出されている
一九五八および五九各米会計年度における米国の右援助額はそれぞれ二五〇万ドル、昭和三十三年度の本計画国内資金は約五億七千万円であるが、昨年(歴年)中に本計画によつて米国に派遣されたわが国の視察団は、中小企業関係九チーム一一〇名、労働団体関係一〇チーム一〇九名、鉱工業関係三二チーム三四六名、農林関係一四チーム九七名、計六五チーム六六二名に達した。
なお、本計画開始以来一九五九米会計年度までの米国の援助額累計は約八七〇万ドル、昨年までに米国に派遣された視察団は約一六○チーム、一、六〇〇名に達している。
一九五三年発効した現行日米航空協定の附表によれば、わが国に与えられている米国への乗入路線は、日本-ホノルル-サン・フランシスコおよび以遠、日本-シアトルの二路線であるが、航空事業の発展に伴い、わが国としては日本-ホノルル-ロス・アンゼルスおよび以遠の運航を開始することが望ましいとの見地から、現行協定の路線に関する附表を修正してロス・アンゼルスヘの乗入れを実現するため、昨年四月九日から東京において日米両国政府間で正式に協議が行われた。しかしながら、わが国側の希望する新路線、ことにロス・アンゼルス以遠への運航が米国側企業に与える影響等の評価について日米間に意見の相違があり、話合いが纏まらなかつたため、米側代表団は四月二十六日帰国し、その後は在京米大使館を通じて協議が継続されてきた。
結局半歳の時日を費して双方の主張を調整した結果、米側は日本側に対してロス・アンゼルス乗入をみとめるが、従来わが国に与えられていたサン・フランシスコ以遠への無制限の権利は、これをサン・フランシスコ以遠南米を除く地点とロス・アンゼルス以遠南米内の地点との二つに分割することに合意された。
なお右の路線修正の協議に際し、日米航空に関するその他の諸問題についても、日米航空当局代表の間で話合いが行われた結果、航空運送の現段階における発展、貨客量の急激な増大および航空企業の秩序ある発展等は、一九五三年の航空協定を適切に運用することにより十分確保し得るものであるとの合意に達した。
かくて本件協議は、本年一月十四日両国航空当局代表による合意議事録の署名によりすべての議事を終了し、同日藤山外務大臣とマッカーサー駐日米国大使との間に行われた外交公文の交換によつて、航空当局間で合意された路線に関する附表修正がこゝに最終的に確認された。修正された附表によつてみとみられる双方の交換路線は左のとおりである。
日本側路線
1. 日本国から中部太平洋における中間地点を経てホノルルヘ、および以遠
(a) ロス・アンゼルスヘ、および以遠南米の地点へ
(b) サン・フランシスコヘ、および以遠南米を除く地点へ
2. 日本国から北太平洋およびカナダにおける中間地点を経てシアトルヘ
3. 日本国から沖縄へ、および以遠
米国路線
1. 合衆国(アラスカを含む)からカナダ、アラスカおよび千島列島における中間地点を経て東京へ、ならびに以遠
2. 合衆国(その属領を含む)から中部太平洋における中間地点を経て東京へ、ならびに以遠
3. 沖縄から東京へ
(イ) 一九五三年六月に発効した日米加三国の「北太平洋の公海漁業に関する国際条約」に基き、わが国は西経一七五度の暫定線以東の水域におけるさけ・ます漁獲、ならびに北米沖合のにしんおよびおひよう(ハリバット)の漁獲を自発的抑止してきているが、前述三国の委員によつて構成されている北太平洋漁業国際委員会は、これらの漁業資源に関する広汎な科学的研究を行い、当該魚種が引続き条約に定める自発的抑止の条件を具えているかどうか、また前記の抑止線が果して妥当であるが否かなどについて検討する任務を与えられている。
米国は、一昨年のヴァンクーヴァーおける委員会第四回定例年次会議以来、暫定線西側の近接水域における日本側の沖合さけ・ます漁業が北米系さけ・ます資源、就中ブリストル湾のべにざけ資源に著しい影響を与えているとの立場をとり、同水域における日本側の漁獲制限が必要であり、最終的には現行暫定抑止線をさらに西方へ移動せしむべきであるとの主張を繰返している。これに対してわが国は、海洋資源に依存するところの大きい漁業国として漁業資源の合理的保存には深い関心をもつており、右に必要な措置であればこれを考慮するにやぶさかでないが米側の主張には十分な科学的裏付けがないとの立場をとつてきている。
(ロ) 昨年十一月東京で開催された委員会第五回本会議では、まず生物学調査小委員会において、日米加三国の生物学者から、アジア北米両大陸系さけ・ますの判別方法およびその分布について従来行われてきた各種の調査研究の結果が発表された。これら研究の方法論およびこれによつて得られた調査結果の確実性について、三国生物学者の間に活発な意見の交換が行われた後、小委員会の結論としては、暫定線の東西にわたる広汎な水域で両大陸系のさけ・ますが混交していることはみとみられるが、その量的な分布については、なお十分な知識が得られていないという報告が行われた。このため米国側としても、北米系さけ・ます、とくにブリストル湾のべにざけ保護のために抑止線をさらに西方へ移動せしめることが望ましいという従来の主張を繰返し表明しつつも、これを正式の提案として持出すまでには至らず、結局現行抑止線はそのまゝ据置かれることとなつた。
なお委員会に与えられているいま一つの重要な任務は抑止魚種の抑止条件(当該資源が米加側によつて科学的な保存計画の下に完全に利用されていることなど)を検討することであるが、この点について日本側は北米系さけ・ます、にしん、おひようのいずれについても充分な抑止条件を具えているという証拠は得られていないとの見解を述べた。しかし米、加側は抑止条件は合理的な程度に満されているとの立場をとり、結局三国の一致した見解は得られなかつた。なお条約規定によれば、抑止条件が存続しなくなつたことにつき三国の一致した同意が得られないかぎり、これらの魚種は引続き抑止の対象となることになつている。
北太平洋のおつとせいに関する新条約は、一九五五年十一月からワシントンで日米加ソ四カ国間で交渉され、(「わが外交の近況」第一号五八頁参照)、一年二カ月にわたる交渉の後、一昨年二月、「北太洋のおつとせいの保存に関する暫定条約」として署名され、同年十月十四日発効した。その骨子は、締約国によるおつとせいの商業的海上猟獲を暫定的に禁止し、その間おつとせい資源を科学的に調査し、かたがた繁殖島を保有する米、ソ両国は陸上で捕殺したおつとせいの獣皮を繁殖島を持たない日加両国に対し一定比率で配分するというにある。
この条約に基き、「北太平洋おつとせい委員会」が設立され、毎年一回年次会合を開催し、前年度の協同科学調査の結果および次年度の調査計画の細目等について討議することとなり、その第一回および第二回年次会合は、いずれもワシントンで開催された。
なお右条約の獣皮配分規定に基き、わが国は昨年末までに、米国より四四、三〇五枚、ソ連より一、九四六枚計四六、二五一枚のおつとせい獣皮を受領している。
都市相互間の文化の交流ならびに観光、貿易等の振興を目的として、近年わが国の都市と米国の都市との提携が漸次増加しつゝあるが、その現状は、本年一月十六日現在次表の通りである。
日米両国都市間の都市提携状況
(昭和三四、一、一六現在)
日本側都市名 米側都市名 発足年月日
1 長 崎 市 セントポール市(ミネソタ) 昭和三〇、一二、二四
2 横 浜 市 サンディエゴ市(カリフォルニア) 〃 三一、一〇、二九
3 仙 台 市 リヴァーサイド市( 〃 ) 〃 三二、 三、二九
4 岡 山 市 サン・ノゼ市( 〃 ) 〃 三二、 五、二五
5 三 島 市 パサディナ市( 〃 ) 〃 三二、 八、一五
6 神 戸 市 シアトル市(ワシントン) 〃 三二、一〇、 七
7 大 阪 市 サンフランシスコ市(カリフォルニア) 〃 三二、一〇、二一
8 館 山 市 ベリンハム市(ワシントン) 〃 三三、 七、一一
9 下 田 市 ニューポート市(ロードアイランド) 〃 三三、 五、一七
10 甲 府 市 デ・モイン市(アイオワ) 〃 三三、 八、一六
11 京 都 市 ボストン市(マサチュセッツ) 話 合 中
戦犯問題については、政府は、解決しうるものから速やかに解決するとの立場に立つて鋭意処理を進め、昨年九月
藤山外務大臣が渡米した際も、米国政府に対し重ねて本件の早期解決方を要請した結果、昨年十二月末をもつて戦犯
問題は左のとおり完全に解決した。
A 級 戦 犯
一九五六年三月末をもつてA級戦犯者全員が仮出所が実現したが、これらの者は仮出後もなお保護監督下に置かれている状態であつたので、日本政府は、米国政府をはじめ関係国政府に対しその赦免方を要請していた。しかるところ昨年四月七日在京関係国公館より、対日平和条約第十一条に基き、A級戦犯者全員が同日までに服役した期間までその刑を減刑する旨の通報があつたので、ここにA級戦犯問題は完全に解決するに至つた。
B、C級戦犯
一昨年十二月末現在巣鴨に在所中の米国関係B、C級戦犯者は四十五名であつたが、同年十二月に設置された戦犯釈放促進のための調査会が、米国政府より貸与を受けた裁判記録に基いて一覧を作成し、右所見を基として、日本政府より米国政府に対しこれらの者の仮出所許可方を要請した結果、昨年五月二十日付をもつて全員の仮出所が実現した。
政府は、その後さらに仮出所中の米国関係B、C級戦犯者三六〇名をも前記のA級戦犯と同様な方法で速やかに赦免するよう米国政府に要請した。その結果これらの者についても逐次減刑、赦免が許可され、同年十二月二十九日付をもつて全員の赦免が実現した。なほ仮出所のオランダ関係B、C級戦犯一二八名も同年十二月五日付で全員減刑赦免されたので、ここに戦犯問題は完全に解決をみることとなつた。