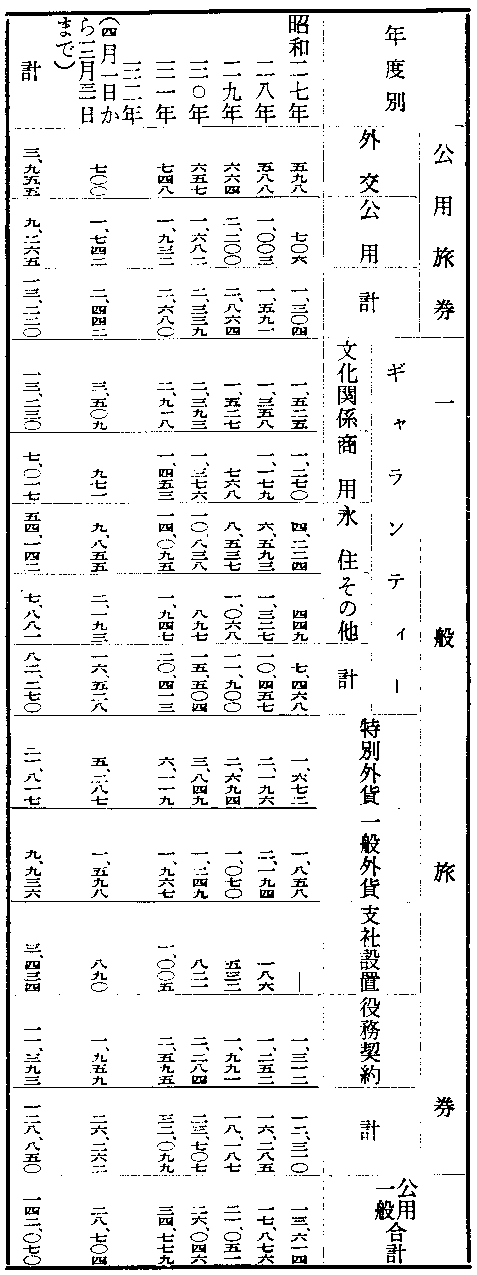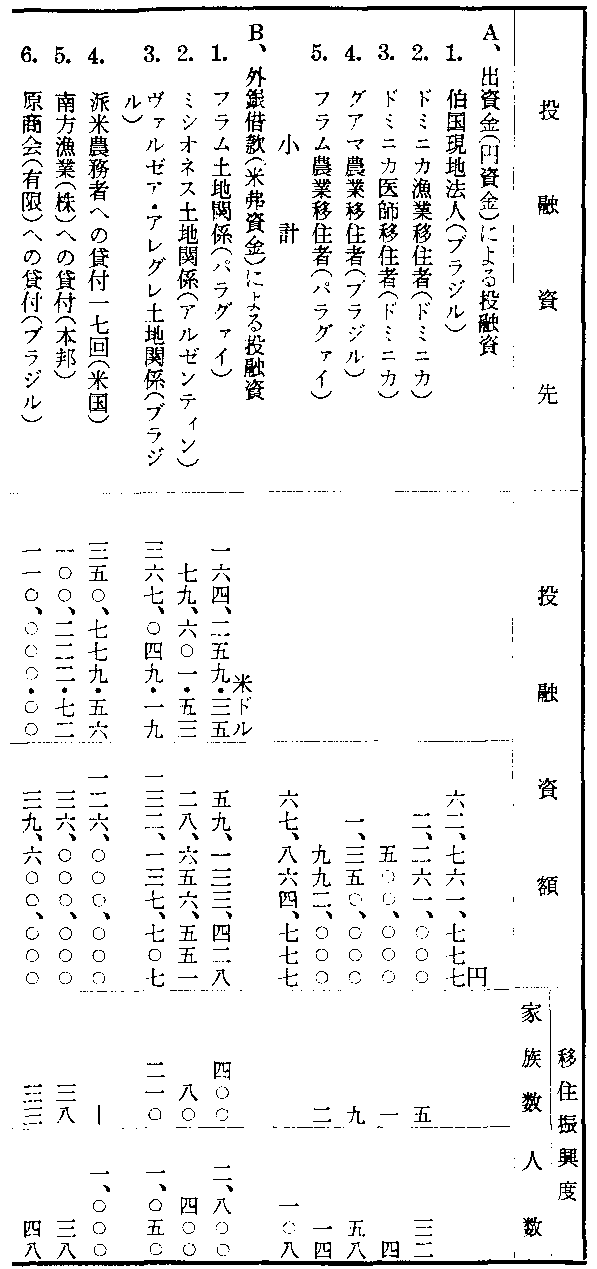
五 海外移住の現状
昭和三十二年三月パラグァイ政府より、同国の閣議決定にもとづく、商船隊建造のための借款の申し出があり、同八月、黒田公使からそのため調査団派遣方の要請があつた。そこで政府は九月、運輸省係官を先発せしめ、十月、大阪商工会議所会頭杉道助特使を団長とするパ国造船計画および移住調査団を派遣し、船舶建造等に関する調査を行わしめた。(特集五参照)
この借款は航洋船五隻ほか河船等四隻、浮ドック一基を日本で建造するために必要な資金として、大体四十三億円をわが国から借入れたいというものである。パラグアイ政府は、この借款が実現すれば、三十年間毎年五千人づつ、計十五万人の日本人移住者を受入れる案を提示してきた。なお先方は調査団の訪問を多として、とりあえず二百家族分の移住用地として、ユー地方の四千町歩を無償で提供してきた。
この問題はパラグァイの経済発展に対する協力の意味からも、わが国移住政策の発展の意味からも、重要な性質をもつているので、三十二年十二月、現地から黒田公使を一時帰国せしめて、現地情勢等を聴取するとともに借款の実現方を推進した。
ところが三十三年度予算において、日本海外移住振興株式会社によるこの造船建造融資実施に必要な政府出資三十億円が認められなかつたため、輸出入銀行による融資等の別途方法を検討中である。
(1) 昭和三十一年にはわが国の国際連合への加盟も認められたので、国連を通じてわが国の移住を促進するための国際与論を喚起する必要を認め、藤山外相は三十二年九月に開催された第十二回国連総会で次のような趣旨を力説し、参加国に大きな感銘を与えた。
「今日の世界には人口の過剰に悩む国と未開発の土地や資源をもちながら開発のため、人的資源を必要とし、移住者の受入れを望んでいる国とがあるので、国際連合がこれらの国々の間に立つて調整の役割を果し、過剰な労働力、技術および資本を利用し得るようあつせんに当ることを希望する。さらに関係国のみのためばかりでなく、全世界の福祉のため将来は移住が世界各国間にいつそう自由になることを希望する。
(2) 昭和三十二年八月五日から九日までジュネーヴで開かれた非政府移住関係機関国際会議に在ジュネーヴ代表部の千葉書記官をオブザーバーとして出席させ、わが国移住の現況について報告させるとともに、参加諸機関の協力を要請させた。
(3) 昭和三十二年九月二十二日から同二十六日まで五日間、イタリアのアッシジで第三回国際カトリック移住委員会が開催された。在ヴァチカン鶴岡公使および在伊大使館安倍参事官がこれに出席したほか日本側委員として田口司教、佐々木神父、海外協会連合会副会長坂本龍起の三氏が参加した。外務省はこの会議の重要性にかんがみ、日本の移住問題の実態、隘路、障害等に関する文書、図表、写真等の資料を作成送付し、図表、写真の主なるものは会場に展示するよう手配した。わが方のこうした処置と、出席者の努力により会議全体の日本にたいする認識を深め、日本の移住者が同化を通じて移住先国の繁栄に貢献していることを認め、かつ次回会議において日本の過剰人口問題をとりあげる旨の決議を可決した。
三十二年五月、岸総理がパキスタンを訪問したさい、同国大統領からわが国の移住者を受入れるため、五千エーカーの土地を提供する旨の好意的申出を受けた。政府としては、この移住を実施するには、移住者を成功せしめる社会的、経済的および自然的条件を綿密に調査し、移住者の将来に十分の見透しを得た上でなければならないと考え、慎重に検討している。
ブラジル
北ブラジル 三十二三十二年度には十二月までグァマ植民地、マザゴン植民地に計画移住者を四六七名送出し、その他、アカラ植民地、ベレーン近郊等に呼寄せ移住者九九名を送出した。三十三年度には、グァマ植民地、モンテ・アレグレ植民地およびマラニョン州の植民地等に多数の計画移住者の送出を計画している。
中部ブラジル 三十二年度においてはブラジル側の受入れ準備がととのわなかつたため、この地域への移住はなかつたが、三十三年度には、リオ・グランデ・ド・ノルテ州、バイア州、ペルナンブコ州等へ数十家族の送出が見込まれている。
南ブラジル 三十二年度は十二月までに計画移住者として養蚕移住者一四九名、コチア産業単独移住者四八四名、計六三三名を送出したほか、呼寄せ雇用移住者として二、九六〇名を送出した。三十三年度には、このほか日本海外移住振興会社がマット・グロソ州に購入した分譲地への自営移住者の送出も予定している。
パラグァイ
三十二年度は四〇〇家族入国許可に基きフラム地区(日本海外移住振興会社が三十一年七月購入した一万六千町歩)に十二月末現在ですでに一一五家族七三四名を送出した。
その他米人所有のペドロ・ファン・カバリェロ耕地(通称CAFE耕地Compania Americana de Fomento Economico)にコーヒー栽培のため雇用移住者として本年度十二月末現在で五一家族三二九名が導入された。
ドミニカ
三十二年度には十二月末現在六九家族二九九名を送出した。なお、コーヒー栽培育成のため一五〇家族受入れの申し込みあり、三十三年三月船から三〇家族づつ分割送出の準備を進めているが、その他の開拓移住者をも含め三十三年度には二〇〇家族程度送出の予定で目下計画中である。また現在ドミニカがわが国移住者に与えている諸般の受入条件を政府間の正式取極めにするため移住協定を交渉中である。
アルゼンティン
三十二年一月アルゼンティン政府はこんご五カ年間に四〇〇家族の入国を許可してきたが、これは各年かつ各州につき八〇家族を超えないことを条件としている。政府は日本海外移住振興会社をしてミシオネス州に約三千町歩の土地を購入させ、これを三〇町歩づつ八〇家族に分譲することとし最初二〇家族を三十三年早々送出するよう準備を進めている。
ボリヴィア
三十二年度には十二月現在で四七家族二六五名を送出したが、なお年度内に七〇家族を二回に分割送出するよう準備中である。
ヴェネズエラ
ヴェネズエラでは移民法により有色人種は入国を許されていないため、わが移住者の進出が阻害されて来たが、本年度にいたり初めて呼寄せの形式で農業移住者四家族二三人が導入され、こんごの先例を開いた。従つて当分はこの方式により少数づつ優秀なものを送出する方針である。
難民救済法および修正移民国籍法によるもの
一九五三年の難民救済法(主として欧州の難民の移住を主眼としたものである)により、わが国からも一、〇〇六名が渡米したが、この法律は、一九五六年末をもつて失効したため、米側の審査に合格した約一、〇〇〇名が渡航不能となつた。我が方としては同種法律が再び制定され、これら渡航不能となつた難民が渡米できるよう希望している。
なお、一九五七年九月十一日制定の修正移民国籍法第十五条によれば、共産圏からの避難民に対し難民救済法による未使用査証数を限度として米国への移住を許しうることになつているので、わが方では目下その日本人引揚者への適用方につき米側と折衝中である。
農業労務者短期派米計画によるもの
計画実施までの経緯 カリフォルニア農場に日本人を導入する構想は、一九五二年ごろから日米双方で進められたが、この計画は米国労働組合の阻止運動などで一時挫折した。そのご一九五三年に難民救済法が制定され、同法にもとづき約一千名の日本人が主としてカリフォルニア農場に導入され、その成績にかんがみ、再び前記移民国籍法による短期日本人農業労務者導入の動きが生れ、わが方で一九五六年春いらい、米国連邦政府およびカリフォルニア農業者団体と折衝を重ねた結果、同年七月米国政府は一千名の導入を承認するにいたつた。この承認に先立ち、わが方ではこの事業の実施機関として農業労務者派米協議会を設立して、国内の送出態勢をととのえ、米国政府の承認後直ちに作業を開始し、同年九月から翌年五月までに一千名の送出を完了した。
第二年度計画の現状 一九五七年度の送出については、受入れ側であるカリフォルニア農業者団体とも話し合い、先方からは年間三千名程度への増加を要望されたが、諸般の考慮からわが方は前年度同様一千名の派遣を主張したところ先方もこれを諒承し、じらいこれに基き送出計画を進めてきた。ところがこの受入れ承認の問題に関し米国政府部内の意見がまとまらず、同年四月から五月にかけて下院法務委員会はカリフォルニア現地およびワシントンで日本人短農受入れの可否に関する公聴会を開いた。その結果、同委員会としてはこの事業の継続および拡大を条件付で認める勧告を採択した。しかし、行政部内に意見一致しない点があつたので同年八月、国務、法務、労働三省からそれぞれ代表者一名を参加させて現地調査を行つた結果、日本人短農をスト破りに使用しないこと、その他受入化条件改善に関する諸条件を雇用者側が認めるならば、こんご毎年一千名の日本人を受入れてもよいということになつた。しかし、雇用者側ではこの条件の受諾につき意見が一致せず、目下この諸条件をめぐり雇用者側と米国政府との間に交渉が行われている。
計画の意義 この計画は日本農村の経営改善、二、三男対策等の重要問題の解決に寄与し、やがて農村の中堅となる青年に国際的視野をもたせ、人口過剰と耕地過小のため行悩んでいる日本農村青年に大きな光と希望を与えるものであり、政府としては日米協力関係の最も有力な一環として本事業を慎重にかつ強力に推進する方針である。
西独における国内炭鉱労務者不足と日本側の労務者教育目的とがたまたま合致したので、三十一年十一月二日、日独両国間に取極が成立し、これにより三十二年一月炭鉱労務者の第一陣五九名が渡独した。第一陣労務者の現地における成績は極めて優秀であり、現地から後続者の送出を強く希望してきたので後続陣として一八○名が三班に分かれ、三十三年一月から毎月一班づつ出発することになつている。この計画は労務者教育を目的としている計画で、派遣労務者は、日本の石炭企業会社で現に就労している者のなかから選抜され、三年後に帰国すれば再び出身会社に復帰するものであるから一般公募をしていない。
戦後昭和二十七年に移住が開始されてから、三十二年十二月末までの送出実績は次表の通りで、約二万一千人である。(これは政府の渡航資金の貸付を受けて渡航した者のみの数であるから、このほかに呼寄せその他の方法で移住した者はかなり多い。)このうちほとんど大部分が農業移住者である。
三十一年度には六、一五五人を送出したが、三十二年度にはサントス丸改装船の就航もあり、十二月末までにすでに約六千人を送出した。残り三カ月間の三十二年度内にはさらに二千数百人を送出する予定である。
三十三年度には五月以降新造船アルゼンティナ丸の就航によりさらに輸送能力が増強されるので、一万人(政府渡航者貸付分のみ)の送出を見込んでいる。
単独青年の移住希望者が非常に多いので、政府もできるだけ多くの青年を出すようにしている。現に行われているものは呼寄せ形式によるものは別として、サンパウロのコチヤ産業組合、同じく東山農場、サンパウロ農業拓植協同組合中央会等が受入れ先きになつている。ほかに外務省が直接扱つている海外実習生があり、これはブラジルのみに限らないが、これを入れて全体で年間五、六百人の青年の移住ができることになつている。サンパウロ農業拓植協同組合中央会は、現地に産業開発青年隊訓練所を設立し、青年の技術能力を高めながら、これを受入れる基盤の拡大をはかつている。
中小企業者の移住促進についても、現地公館を督励し、できるだけの処置を講ずることとしている。ブラジルについては、すでに着々実績をあげているが、これは農業移住者の場合のように一挙にある数にまでもつて行けるという性質のものではない。言葉、資本の問題のほかに、その国の法律的制約の問題もある。たとえばブラジルでは、あらゆる事業を通じ、外国人を雇用する場合は、外国人一人について同時にブラジル人を二人雇用しなければならないこととなつている。また中小工場を経営するにしても、他の関連工場に部分品を求めるという便宜がないから、その工場は非常に広い範囲にまで作業をひろげなければならぬという事情もある。それはそれでよいとしても、当然資本の問題も起つて来る。しかし移住はもはや、農業者、農業労働者のみに限られるべきでなく、もつと広く多種類の移住を促進する必要があり、中小企業の移住については、とくに力を入れて行く方針である。
国内における移住業務の第一線機関は都道府県海外協会である。全国都道府県にこれができている(京都府は直接府庁開拓課が担当)が、その業務の主なのは移住に関する啓発、募集、相談および送出手続等である。日本海外協会連合会は、その中央機関であると同時に、また海外各地に支部をおき、日本からの移住者受入れ、営農指導等に当つている。
日本人の移住先国は、もちろんみな完全な独立国であり、移住者の本国の機関の立入つた指導を好まないが、適当な範囲内で、移住者の自立定着を指導したり、援助したりすることは一般に認められているので、大体海協連支部をしてこれを行わせている。移住者の到着のさいの世話等も一切これが引受けていることはいうまでもない。ただアルゼンティンではこの種業務をアルゼンティン拓植協同組合が行つている。海協連支部所在地はつぎの通りである。
リオ・デ・ジャネイロ、サンパウロ、ベレン(以上ブラジル)、ボリヴィア、パラグァイ、ドミニカ、サンフランシスコ
移住事業に関して資金面の援助を担当している日本海外移住振興株式会社(社長大志摩孫四郎)は、現在、ブラジル国リオ・デ・ジャネィロ(本店)、サンパウロ(支店)およびベレーン(支店)に同国法律に基き設立された現地法人、パラグァイ国アスンシオンに支店、アルゼンティン国ブエノスアイレスに駐在員事務所を設置して、いよいよ実際活動の段階に入つた。
会社は、政府および民間の出資による資本金八億円(なお昭和三十二年度予算においてさらに五億円の出資が計上されている)と米国三銀行との間に締結された移住借款契約にもとづく借入金(第一回借入金一五〇万ドル、第二回借入金一五〇万ドル)を資金として事業を行つており、現在までに同社が貸付または投資を行つた金額は、約八億五千万円である(次表参照)。この事業実績のうち主なものは次のおりである。
移住用地の購入
フラム移住用地 会社は、パラグァイ国のフラムに移住用地として面積約一六、五〇〇ヘクタールの土地を購入、これを造成の上、移住者への分譲を行つており、すでに日本から三十二年十二月末現在一九二家族が入植している。同移住地には、総計四〇〇家族が入植しうる予定である。
グアルアッペ移住用地 会社は移住用地として、アルゼンティン国ミッショネス州グアルアッペに、面積三、一二五ヘクタールの土地を購入した。この移住地購入に伴い戦後初めての開拓移住者四〇〇家族(五年間、年八〇家族)がアルゼンティンに入植を許されることとなつたが、同移住地への入植開拓は本年度末頃の予定である。
ヴァルゼア・アレグレ移住用地 移住用地としてブラジル国マット・グロッソ州ヴァルゼア・アレグレに約四〇、〇〇〇ヘクタールの土地を購入した。右移住地には約二一〇家族の移住者が入植しうる計画で、現在会社は土地造成を行いつつあるが、入植開始は昭和三十三年度となる予定である。
派米農業労務者に対する渡航費の貸付
米国カリフォルニアで就労する派米農業労務者に対し渡航費の貸付を行つている。現在までの被貸付者数は一、〇〇〇名である。
その他の貸付および投資
移住者または日本からの移住者を受入れる企業に対し、会社が貸付および投資を行つた件数は、現在までのところ十三件であるが、こんご企業移住振興の見地から、なおこの種業務の促進が期待される。
なお、会社は、戦後移住者の半ばを占めている開拓移住者が現在緊急に必要としている共同利用農機具施設(脱穀機、精米機、製粉機等)および交通運搬機関(ジープ、トラック等)等を取得するための資金貸付も実施している。
昭和三十二年十二月末日現在
 |
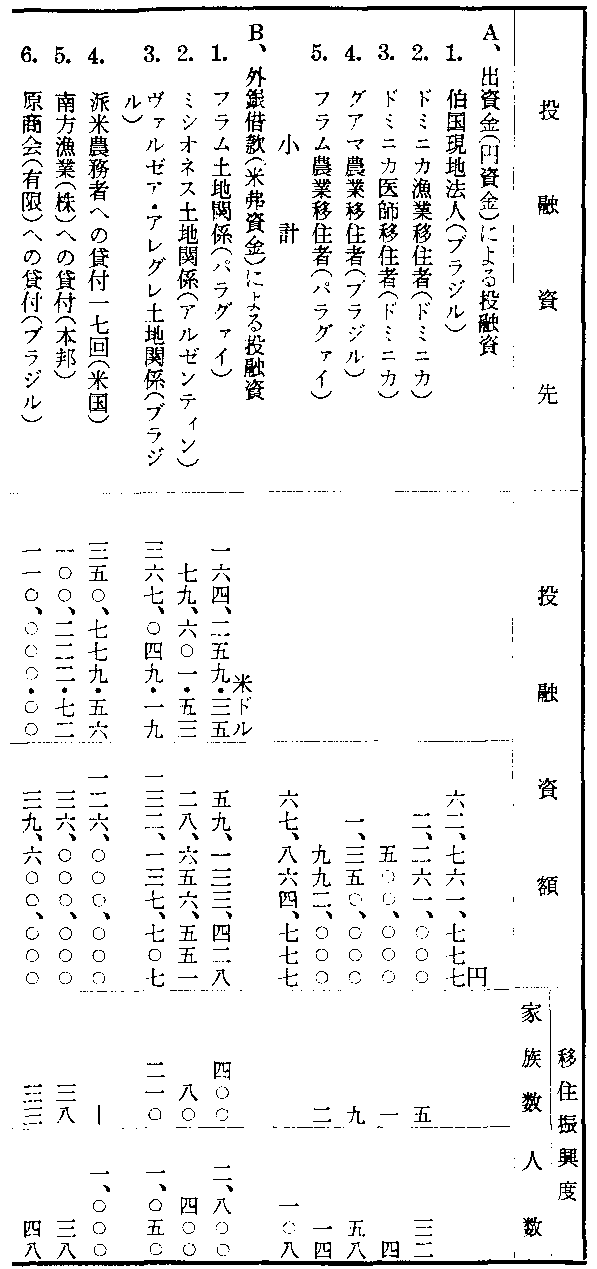 |
(注) ただし、この表B項中派米農業労務者および南方漁業の円貨金額は、米ドル資金による円貨貸付につき、三五九、一一〇円替であり、その他はドル送金につき帳簿表か換算率三六〇円替として算定した。
最近における世界景気の頭打ちと政府の金融引きしめ措置等により、伸びなやみの状態にあるわが経済事情に左右され、これまでいちじるしい増加ぶりを示した邦人の海外渡航は、一昨年十一月頃からようやく横ばいの傾向をたどつているが、三十二年度は上期の好調に支えられ昨年四月から十二月にいたる九カ月間の渡航者数は計二八、七〇四人を数え、年度末までには昨年度の三四、七七九人を相当上回る見込みである。
前記本年度九カ月間の海外渡航邦人の目的別内訳は従来どおり永住者が筆頭を占め、九、八五五人、以下商用七、四八六人、文化関係四、一五九人、役務契約一、九五九人等の順序となつている。
昭和二十七年度以降年別渡航者数は左表のとおりである。